建設業許可は個人事業主(一人親方)でも取得できる!条件・費用・流れを徹底解説!
建設業許可は個人事業主(一人親方)でも取得できる!条件・費用・流れを徹底解説!

「建設業許可は法人じゃないと無理なの?」 「個人事業主(一人親方)でも建設業許可は取れるの?」「一人親方でも500万の財産要件は必要?」
このような疑問をお持ちの方は少なくないのでしょうか。結論から申し上げますと、個人事業主(一人親方)でも建設業許可を取得することは可能です。
しかし、法人と比較して取得のハードルが高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、個人事業主が建設業許可を取得するための条件、具体的な流れ、そして注意点について解説します。
これから一人親方として建設業許可の取得をお考えの方に、ご参考にしていただけると幸いです。
目次
090-9451-9906(茂木)
1|建設業許可とは?なぜ個人事業主にも必要なのか
建設業許可とは、建設工事を請け負う際に、請負金額が一定額以上になる場合に必要となる許可です。具体的には、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)の建設工事を請け負う場合に、建設業許可が必要となります。
この許可制度の目的は、発注者保護と建設業の健全な発展です。無許可業者が横行すると、手抜き工事やトラブルが増加し、業界全体の信頼性が損なわれてしまいます。そのため、一定の技術力や財産的基礎を持つ業者にのみ許可を与えることで、質の高い建設工事を担保しているのです。
個人事業主であっても、大規模な工事や公共工事を受注するためには、この建設業許可が必須となります。無許可で請負金額が500万円以上の工事を請け負った場合、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となるため、注意が必要です。
2|個人事業主が建設業許可を取得するメリット・デメリット

個人事業主が建設業許可を取得することには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 請負金額の上限撤廃: 500万円以上の工事を受注できるようになり、事業規模を拡大できます。
- 公共工事の受注機会の増加: 建設業許可は、公共工事の入札参加資格の前提条件となることがほとんどです。
- 元請業者との信頼関係構築: 許可を持っていることで、元請業者からの信頼を得やすくなります。下請業者としてだけでなく、元請業者として仕事を受けるチャンスも広がります。
- 社会的な信用の向上: 許可業者は、一般消費者や取引先から見て、より信頼できる事業者と認識されます。
デメリット
- 要件のクリアが難しい場合がある: 特に「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を満たすのが、個人事業主にとってはハードルとなることがあります。
- 申請準備に時間と手間がかかる: 必要書類が多く、収集や作成に時間と労力がかかります。
- 取得・維持費用がかかる: 申請手数料や、許可取得後の更新費用、場合によっては行政書士への依頼費用などが発生します。
- 許可取得後の義務: 帳簿の備え付けや決算報告書の提出など、許可業者としての義務が発生します。
これらのメリットとデメリットを比較検討し、ご自身の事業の方向性に合わせて許可取得の是非を判断することが重要です。
090-9451-9906(茂木)
3|個人事業主が建設業許可を取得するための要件
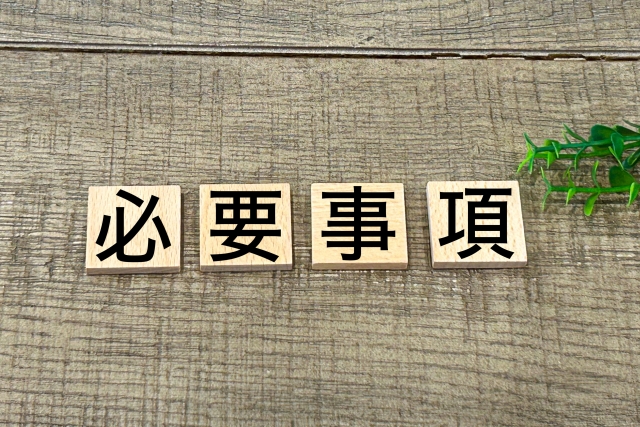
建設業の許可を取得に必要な主要要件を解説します。その中でも、特に「経営業務の管理責任者の配置」と「営業所技術者の配置」は人的要件と呼ばれ、難易度が高い要件となっています。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置
建設業の経営を適正に行うための体制を確保する要件です。
- 要件の概要: 建設業の経営業務について一定の経験と実績を有している必要があります。
- 例: 建設業に関して5年以上の経営経験、または6年以上の経営業務を補佐する経験などが必要です。
ポイント: 2020年(令和2年)の法改正により、要件が柔軟になりましたが、一般的には「5年の経営経験」で証明するケースが多いです。
関連記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
2.営業所技術者の配置
建設業の許可を受けた営業所において、請負契約の適正な締結や履行を技術的な側面から確保するための要件です。
- 要件の概要: 各営業所ごとに、その業種に関する専門的な知識や実務経験を持つ技術者を、常勤かつ専任で配置する必要があります。
- 例: 以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 資格保有者: 対象の国家資格(例:建築施工管理技士や〇〇技能士など)を持っている。
- 実務経験者: 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験がある(指定学科を卒業している場合は、3年または5年に短縮可能)。
ポイント:同一営業所内であれば、一人の人間が「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」の両方の要件を満たしている場合、一人二役を兼ねることができます。
個人事業主(一人親方)で建設業許可を取得する場合は、「経営業務の管理責任者」と兼任する場合がほとんどです。
関連記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
3. 適切な社会保険への加入
建設業で働く労働者の待遇改善と、企業のコンプライアンス遵守のため、社会保険への加入は必須の要件となっています。
- 要件の概要: 建設業者が雇用するすべての従業員について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入し、その加入状況を証明することが求められます。(個人の場合は国民健康保険、国民年金。従業員を雇っている場合は雇用保険。)
- 重要性: 適切な社会保険への加入は、今や建設業許可を取得・維持するための重要な前提条件です。未加入や加入手続きの不備がある場合、許可申請は受理されません。
関連記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
4. 財産的基礎・金銭的信用
工事を請け負い、事業を継続していくための経済的な基盤があることを示す要件です。
- 自己資本(純資産の合計額)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)。
特定建設業を取得する際に必要な財産要件は格段に厳しくなります。
関連記事:【建設業許可の要件】財産要件の500万円。無い場合は?融資でもいい?行政書士が徹底解説!
5. 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請者が、建設業法で定められた欠格要件(法律違反による罰則、成年被後見人・被保佐人など)に該当しないことが必要です。
関連記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
090-9451-9906(茂木)
4|個人事業主が建設業許可を取得するまでの具体的な流れ

個人事業主が建設業許可を取得するまでの一般的な流れは以下の通りです。
1.要件の確認と必要書類の収集
まずは、ご自身が上記の要件をすべて満たしているかを確認します。特に経営業務の管理責任者と営業所技術者の要件については、建設業許可の手引きで詳細に確認し、必要な書類を漏れなく収集します。この段階で不足しているものがあれば、どうすれば要件を満たせるのかを検討します。
取得する業種を間違えてしまうと、再度許可の取り直しとなるため業種選択も慎重に行ってください。
2.申請書類の作成
必要書類が揃ったら、建設業許可申請書を作成します。申請書は都道府県庁や国土交通省のホームページからダウンロードできます。膨大な数の書類と記載事項があり、専門知識が必要となるため、非常に手間がかかる作業です。誤字や記載漏れがないよう、慎重に作成する必要があります。
3.申請書の提出
作成した申請書と添付書類を、行政庁に提出します。
- 知事許可: 営業所が1つの都道府県内にのみ設置されている場合。
- 大臣許可: 営業所が複数の都道府県にまたがって設置されている場合。
個人事業主の場合、ほとんどが知事許可に該当します。申請手数料として、新規申請の場合は9万円が必要です。
4.審査
申請書が提出されると、書類の審査が行われます。書類に不備がないか、要件を満たしているかなどが厳しくチェックされます。場合によっては、追加資料の提出を求められることもあります。審査期間は、都道府県によって異なりますが、一般的には1ヶ月から2ヶ月程度かかることが多いです。(群馬県の場合、約一ヶ月)
5.許可通知書の受領
審査が問題なく完了すれば、建設業許可通知書が交付されます。お疲れ様でした、これで晴れて建設業許可業者となります。
許可取得は専門家への依頼が確実です
建設業許可申請は、その要件の多様さと、提出書類の多さ・複雑さから、専門知識なしに進めると時間と労力を大幅に浪費するリスクがあります。
- 要件の正確な判断:
- お持ちの資格や実務経験が、どの業種の許可要件を正確に満たすのか。
- 経営陣の経験や会社の財務状況が、現行の法規制に照らして適格か。
これらの判断には、専門的な知見が必要です。
- 煩雑な書類作成と収集:
- 登記簿謄本、納税証明書、残高証明書、工事経歴書など、膨大な種類の書類を抜け漏れなく、かつ指定された様式で作成・収集する必要があります。
- 許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)とのやりとりや、書類の軽微な修正にも対応しなければなりません。
これらの手続きを本業の傍らで行うことは、想像以上に大きな負担となります。
我々行政書士は、建設業許可の専門家です。
- 結果として、最短で、確実に許可を取得し、大規模な工事を請負うことが可能になります。
- 建設業許可専門の行政書士に依頼することで、貴社の状況を正確にヒアリングし、許可取得の可否や不足している要件を迅速に判断してもらえます。
- すべての書類作成、収集の指示、行政庁との折衝までを一任できるため、皆様は、本業である建設業務に集中することができます。
090-9451-9906(茂木)
5|個人事業主が建設業許可を取得する際の注意点

個人事業主が建設業許可を取得するにあたって、注意すべき点をご紹介します。
1. 個人事業主の屋号
建設業許可は、個人事業主の場合、個人名(氏名)に対して付与されます。屋号を記載することはできますが、あくまで付随的な情報であり、許可の名義は個人名です。ご注意ください。
2. 許可取得後の義務と更新
建設業許可を取得したら終わりではありません。許可取得後も、以下の義務が発生します。
- 決算変更届の提出: 毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要があります。
- 許可の更新: 建設業許可の有効期間は5年間です。有効期間満了前に更新申請を行う必要があります。更新を怠ると、許可が失効してしまいます。
これらの義務を怠ると、罰則の対象となるだけでなく、将来の更新に影響が出る可能性もあるため、計画的に対応していくことが重要です。
6|まとめ:個人事業主の建設業許可取得は、事業拡大への第一歩

今回は、個人事業主が建設業許可を取得するための条件、流れ、そして注意点について詳しく解説しました。
個人事業主であっても、適切な準備と要件を満たせば、建設業許可を取得することは十分に可能です。許可取得は、500万円以上の大規模工事や公共工事の受注を可能にし、信用力を向上させ、将来的な事業拡大の大きなきっかけとなります。
要件の確認、必要書類の収集、そして申請書類の作成は大変な作業ですが、諦めずに取り組むことで、新たなビジネスチャンスを掴むことができます。もし、ご自身での手続きに不安がある場合は、我々行政書士などの専門家へ依頼することで確実に取得することが可能です。
090-9451-9906(茂木)
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。



