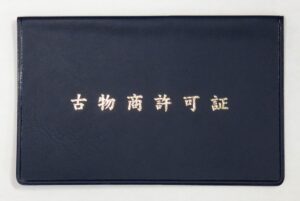補助金と助成金の違いを徹底解説!あなたの事業に最適な公的支援を見つける方法
補助金と助成金の違いを徹底解説!あなたの事業に最適な公的支援を見つける方法

事業を営む上で、資金調達は常に大きな課題です。そんな時、国や地方自治体が提供する「補助金」や「助成金」といった公的支援は、返済不要な資金として、企業の成長や新たな挑戦を力強く後押ししてくれる可能性があります。
しかし、「補助金と助成金って一体何が違うの?」「うちの会社はどっちが貰えるのだろう」と疑問に感じる方も少なくないと思います。一緒にされがちなこの二つですが、実はその目的、管轄している庁、申請の難しさ、そして受給までの過程において明確な違いがあるのです。
今回は、補助金と助成金を徹底的に比較し、申請を成功させるためのポイント、そして専門家の活用方法まで、詳しく解説していきます。
目次
1: 補助金と助成金の基本的な違い
まずは、補助金と助成金の最も重要な違いから見ていきましょう。
| 項目 | 補助金 | 助成金 |
| 管轄省庁 | 主に経済産業省(中小企業庁) | 主に厚生労働省 |
| 目的 | 新規事業、設備投資、技術開発、販路開拓など、企業の事業拡大や生産性向上、経済の活性化 | 雇用環境の改善、人材育成、従業員の福利厚生など、労働環境の整備や雇用の安定・促進 |
| 審査 | 競争的審査(採択制)。事業計画の優位性・実現性が問われる | 要件を満たせば原則受給可能(先着順や予算上限がある場合あり) |
| 公募期間 | 短期集中(数週間~1ヶ月程度) | 通年募集や比較的長い期間で募集されることが多い |
| 支給額 | 数十万円~数億円と幅広く、大規模な事業にも対応 | 数十万円~数百万円程度で、比較的少額 |
| 受給までの期間 | 事業実施後、精算払いが一般的(数ヶ月~1年以上) | 申請から比較的短期間で支給されることも多いが、数ヶ月を要することも |
このように、両者は「返済不要の資金」という共通点はありますが、その性質はかなり違います。
2: 補助金の概要:事業成長を加速させる戦略的資金
補助金は、主に経済産業省(中小企業庁)が管轄し、中小企業の競争力強化や地域経済の活性化を目的としています。
2.1. 補助金の目的と代表例
補助金の目的は多岐にわたりますが、共通して言えるのは「国の政策目標に合致する事業活動を後押しする」という点です。代表的な補助金は以下のようなものがあります。
- 事業再構築補助金: 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、事業再構築に挑戦する企業を支援。新規事業への参入、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰、これらの取組を通じた規模の拡大などを支援します。
- ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金): 革新的な製品開発やサービス提供、生産プロセス改善のための設備投資などを支援し、中小企業の生産性向上を目的とします。
- IT導入補助金: 中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や生産性向上を促進します。
- 小規模事業者持続化補助金: 小規模事業者が販路開拓や生産性向上に取り組むための経費の一部を補助し、持続的な経営を支援します。
これらの補助金は、企業の変革や成長を促すための「戦略的な投資」と言い換えることができます。
2.2. 補助金の申請と採択の壁
補助金の申請プロセスは、助成金と比較して複雑であり、高い専門性が求められます。最大の壁は「採択」という競争的な審査です。
- 公募要領の熟読: まず、申請したい補助金の公募要領を隅々まで読み込み、自社の事業が対象となるか、どのような要件を満たす必要があるかを確認します。
- 事業計画書の作成: 補助金申請の成否を分けるのが、この事業計画書です。単に事業の内容を記載するだけではなく、以下の点を明確に盛り込んでいく必要があります。
- 課題と目的: なぜこの事業を行うのか、どのような課題を解決し、何を達成したいのか。
- 事業内容の具体性: どのような製品・サービスを開発・提供するのか、具体的なプロセスやスケジュール。
- 市場分析と競争優位性: ターゲット市場の規模、競合との差別化ポイント、自社の強み。
- 実現可能性と収益性: 事業が計画通りに進む根拠、売上見込み、費用対効果。
- 地域経済への貢献度: 地域雇用への影響、新たな産業創出など。
- 補助事業の必要性: 補助金がなければこの事業が実施できない理由や、補助金によって事業が加速する理由。
- 必要書類の準備: 決算書、登記簿謄本、各種見積書など、様々な書類を正確に準備します。
- 申請: 公募要領に記載のある日時までに締切厳守で提出します。
- 審査と採択: 書類審査や面接審査を経て、採択の可否が決定されます。採択率は補助金の種類や公募回によって大きく変わります。
- 交付決定と事業実施: 採択された後、正式な交付決定通知を受け、事業を開始します。
- 実績報告と補助金受給: 事業完了後、実績報告書を提出し、初めて補助金が支給されます。原則として、事業実施後に精算払いとなるため、一時的な資金は自社で立替える必要があります。
2.3. 補助金を活用する上での注意点とメリット・デメリット
メリット:
- 返済不要の大きな資金: 事業に必要な大規模な設備投資や研究開発費などを賄うことができ、自己資金の負担を軽減できます。
- 事業の信頼性向上: 国や自治体の審査を通過した事業として、対外的な信頼度が向上します。
- 新たな取引先の開拓: 補助金受給企業として、新たなビジネスチャンスが生まれることもあります。
デメリット:
- 高い競争率と不確実性: 申請しても必ず採択されるわけではなく、不採択のリスクがあります。
- 複雑な申請手続きと時間: 事業計画書の作成や必要書類の準備に多くの時間と労力を要します。
- 資金繰りの制約: 原則として後払いのため、事業実施中の資金は自社で用意する必要があります。
3: 助成金の概要:雇用の安定と労働環境改善のための支援
助成金は、主に厚生労働省が管轄し、企業の雇用環境改善、人材育成、労働者の福利厚生向上などを目的とした公的支援です。
3.1. 助成金の目的と代表例
助成金の目的は、「働く人々の生活を安定させ、企業全体の生産性を高める」という労働政策上の目標に沿っています。代表的な助成金は以下のようなものがあります。
- キャリアアップ助成金: 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善、人材育成などの取り組みを実施した事業主に対して支給されます。
- 人材開発支援助成金: 事業主が従業員に対して、職業訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成します。
- 両立支援等助成金: 仕事と育児・介護の両立支援や女性の活躍推進、男性の育児休業取得促進など、多様な働き方を支援する事業主をが対象となります。
- 業務改善助成金: 中小企業・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
これらの助成金は、企業の「人」への投資を促し、持続可能な経営基盤を構築することを目指しています。
3.2. 助成金の申請と受給の確実性
助成金の最大の特長は、「要件を満たせば原則として受給できる」という点です。補助金のような競争的審査はほとんどなく、提出された申請書類が要件に合致しているかどうかが問われてきます。
- 公募要領の確認: 申請したい助成金の公募要領を確認し、自社の取り組みが対象となるか、具体的な要件を把握します。
- 計画書の作成: 補助金ほど詳細な事業計画書は求められないことが多いですが、助成金の目的に沿った具体的な取り組み内容を記載した計画書を作成します。
- 取り組みの実施: 助成金は、計画に基づいて実際に雇用環境改善や人材育成の取り組みを実施した後で申請するのが一般的です。
- 必要書類の準備: 雇用契約書、賃金台帳、就業規則、訓練計画書、領収書など、取り組みを証明する書類を準備します。
- 申請: 管轄の労働局やハローワークに申請書を提出します。
- 審査と支給: 書類審査が行われ、要件を満たしていれば支給が決定されます。
- 受給: 支給決定後、指定した口座に助成金が振り込まれます。
3.3. 助成金を活用する上での注意点とメリット・デメリット
メリット:
- 高確率での受給: 要件さえ満たせば原則として受給できるため、補助金と比較して資金調達の確実性が高いです。
- 企業のイメージ向上: 従業員を大切にする企業として、対外的なイメージアップに繋がります。
- 従業員のモチベーション向上: 労働環境の改善やスキルアップ支援は、従業員の満足度や定着率を高めます。
デメリット:
- 使途の限定性: 助成金の使途は、雇用環境改善や人材育成など、非常に限定されています。
- 支給額の制約: 補助金と比較して支給額が少額な場合が多いです。
- 継続的な取り組みの必要性: 一部の助成金は、継続的な取り組みが求められる場合があります。
- 書類作成の手間: 補助金ほどではないですが、就業規則の変更や各種証明書類の準備には手間がかかります。
4: 補助金と助成金、どちらを選ぶべきか?判断のポイント
ご自身の事業に最適な公的支援を選ぶためには、以下のポイントを考慮しましょう。
4.1. 事業目的と計画の整合性
・新規事業の立ち上げ、設備投資、販路開拓など、事業の拡大や変革を目指すなら「補助金」の方が有力な選択肢です。
・従業員の採用、教育、労働環境の改善、多様な働き方の導入など、人事・労務に関する課題を解決したいなら「助成金」の方が適しています。
4.2. 資金の必要額と資金繰りの状況
- 大規模な資金が必要な場合は、高額な補助金を検討しましょう。ただし、自己資金である程度の先行投資が必要になることを理解しておく必要があります。
- 比較的少額の資金で、確実な受給を目指すなら「助成金」が適しています。
4.3. 申請にかける時間と労力
- 事業計画書の作成など、時間と労力をかけてでも大きなリターンを狙うなら「補助金」に挑戦する価値があります。
- 日常業務に支障なく、確実に資金を得たい場合は「助成金」の申請から始めるのが良いです。
4.4. 最新の公募情報と要件の確認
補助金も助成金も、制度は常に変化しています。毎年、新しい制度が創設されたり、既存の制度が見直されたりするため、常に最新の公募要領を確認することが重要です。
- 中小企業庁のホームページ
- 厚生労働省のホームページ
- 各自治体のホームページ
これらの公式サイトを定期的にチェックし、自社の事業に合った制度がないか情報収集しましょう。
5: 申請を成功させるための具体的なポイント
補助金、助成金と共に、申請を成功させるためにはいくつかの共通するポイントがあります。
5.1. 事業計画書(または計画書)の質を高める
- 明確な目的意識: 何のために、どのような効果を期待して事業を行うのかを具体的に示します。
- 実現可能性: 計画が空想ではなく、現実的に達成可能であることを裏付けとなるデータや根拠とともに示します。
- 費用対効果: 投資に見合う効果が得られることを論理的に説明します。
- 加点項目への配慮: 多くの補助金や助成金には、特定の取り組みや企業に対する加点項目が設けられています。自社の強みや今後の取り組みがこれに合致しないか確認し、積極的にアピールしましょう。
5.2. スケジュール管理の徹底
補助金は公募期間が短いため、情報収集から申請書類の作成まで、計画的に進める必要があります。助成金も、取り組み実施後の申請となるため、適切なタイミングで準備を進めることが重要です。
5.3. 専門家の活用を検討する
「申請手続きが複雑で自信がない」「事業計画書の書き方がわからない」といった場合は、専門家への依頼を検討しましょう。
- 中小企業診断士: 経営全般のコンサルティングを行い、補助金申請における事業計画策定に強みがあります。
- 行政書士: 官公庁への書類作成・提出の専門家であり、補助金の申請代行を多く手掛けています。
- 税理士: 会計・税務の専門家として、資金繰りや財務状況を踏まえたアドバイスが可能です。
- 社会保険労務士: 助成金の専門家であり、就業規則の見直しや労働環境整備に関するアドバイスに強みがあります。
専門家を選ぶ際のポイント:
- 専門性: 補助金・助成金に対する専門知識を備えているかどうか。
- 信頼して依頼できるか: 信頼して相談できるパートナーであるか、コミュニケーションをしっかり取れるか。
6: まとめ:賢く公的資金を活用し、事業を力強く推進する
補助金と助成金は、それぞれ異なる目的と特性を持つ公的な支援です。
- 事業の拡大や設備投資、新たな挑戦には「補助金」
- 雇用環境の改善や人材育成、従業員の定着には「助成金」
という大まかな指針を理解した上で、自社の現状と今後の目標に合ったものを見つけることが成功への第一歩です。
制度の複雑さや申請の難しさから、申請を諦めてしまう企業も少なくありません。しかし、返済不要の貴重な資金は、あなたの事業が次のステージへと飛躍するための大きな原動力となる可能性を秘めています。
弊所では行政書士として、補助金の申請サポートをさせていただいております。
専門家に依頼することにより採択されやすい事業計画書を作成することができます。
もちろん、事業の見直しや再確認という意味でもまずはご自身で挑戦すると良いかと思います。様々な気づきがあるかもしれません。
もし立ち止まったり、不安だなという状況になった際は、是非ご相談ください。