資格が無くても取れる?実務経験で建設業許可を取ろう!年数や証明方法も解説!
資格が無くても取れる?実務経験で建設業許可を取ろう!年数や証明方法

「建設業の許可(知事許可・大臣許可)」と聞くと、「難しい」「資格がないと無理だ」といったイメージをお持ちの方もいるかもしれません。確かに、建設業を営む上で、一定の基準を満たし、その証拠を提出することは必須です。
特に、許可要件の中でも「専任技術者(現営業所技術者)」の確保は、多くの事業主様にとって大きな壁となりがちです。
「該当する資格が無いとなれない」と思われがちですが、実は
特定の国家資格等がなくても、長年の実務経験を積み重ねることで、この専任技術者の要件を満たすことが可能です。
この記事では、「資格なし」でも実務経験だけで建設業許可を取得するための具体的な要件、必要となる実務経験の年数、そして最も重要となる「実務経験をどのように証明するか」について、徹底的に解説します。これから建設業許可の取得をお考えの方に少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
1|建設業許可のキーパーソン「専任技術者」とは?

建設業許可を取得するためにクリアすべき要件はいくつかありますが、その中でも事業所の「技術力」を示すのが「専任技術者」の要件です。
1. 専任技術者の役割と専任性
専任技術者とは、建設工事の請負契約を適切に履行するために必要な専門的な知識と経験を持つ者として、営業所ごとに常勤で配置される技術責任者のことです。
2. 専任技術者の要件は主に3パターン
専任技術者となるための要件は、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
- 国家資格等を持っている(例:1級/2級建築士、1級/2級施工管理技士など)
- 指定学科の卒業と実務経験の組み合わせ
- 実務経験のみ
このうち、多くの方が注目し、本記事で深掘りするのが3番目の「実務経験のみ」で専任技術者の要件をクリアする方法です。
2|【資格なし】実務経験だけで許可を取るための年数要件
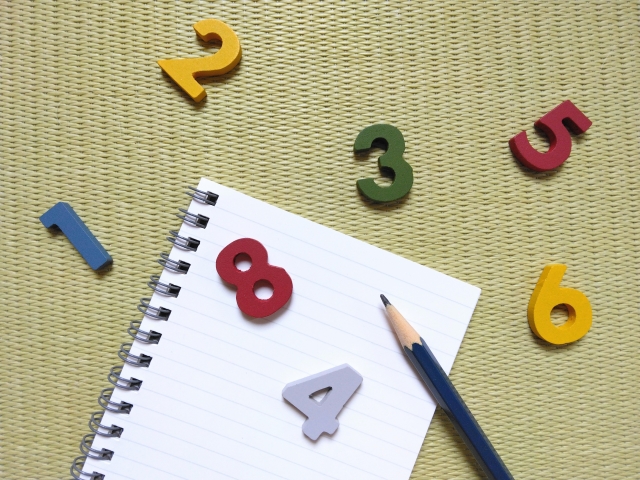
実務経験のみで専任技術者の要件を満たす場合、原則として10年間の経験が求められます。
1. 一般建設業許可の場合:原則10年
一般建設業の許可の場合、原則として、申請する業種について10年以上の実務経験が必要です。
例えば、「とび・土工工事業」の許可を取得したいのであれば、10年以上にわたり、とび・土工工事業に関する工事の施工に携わっていたことを証明しなければなりません。
ただし、以下の特例的な扱いがあります。
- 指定学科卒業者の場合: 高校卒業で5年、大学・高等専門学校卒業で3年、というように、学歴と実務経験を組み合わせることで年数を短縮できます。
- 特定の資格等を有する場合: 準ずる資格や、特定の講習を修了している場合に年数が短縮される場合があります。
2. 特定建設業許可の場合:さらに高度な経験が必要
特定建設業の許可(下請金額の制限が大きい許可)を取得する場合、一般建設業許可の要件に加え、さらに「指導監督的な実務経験」が求められます。これは、発注者から直接請け負った4,500万円以上の建設工事に関して、2年以上の指導監督的な実務経験があることを指します。実務経験のみで特定建設業を目指すのは、極めてハードルが高いと言えます。
また、指定建設業(7業種)に関しては実務経験のみで証明することができないことに注意が必要です。
3|最難関!実務経験の「証明方法」を徹底解説

実務経験で専任技術者を目指すうえで、最も頭を悩ませるのが「どうやって10年間の実務経験を公的に証明するか」という点です。
単に「10年働きました」と申告するだけでは不十分で、客観的な証拠書類を提出しなければなりません。
1. 証明に必要な基本書類
自治体や業種によって若干の違いはありますが、実務経験を証明するために一般的に求められる書類は以下の通りです。
- 実務経験証明書(申請様式):誰が、どの期間、どの業種に、どのような立場で従事したかを詳細に記載する書類。
- 裏付け資料(工事の証拠):
- 契約書・注文書・請書の写し
- 請求書・領収書の写し
- 工事台帳
- 在職証明書(過去の勤務先での経験を証明する場合)
- 健康保険被保険者証の写し(常勤性の確認)
2. 実務経験証明書の「説得力」を高めるポイント
行政庁の審査官が実務経験を認めるかどうかは、提出された書類の「継続性」と「専門性」にかかっています。
【ポイント1:業種との関連性】
証明する工事が、申請する建設業種(例:内装仕上工事業、電気工事業など)の内容に明確に関連していることが必須です。契約書や請求書に記載されている工事名が抽象的でなく、その業種特有の工事であることが判るようにします。
【ポイント2:期間の継続性】
10年間という長期間にわたり、途切れなく、その業種に従事していたことを証明する必要があります。そのため、10年間の間に満遍なく複数の工事の契約書等を提出することが求められます。
- NG例: 10年前に大きな工事を1件、最近大きな工事を1件提出するだけ。
- OK例: 10年間を通して、毎年数件の工事の契約書、請求書を提出し、事業の継続性と実務への従事を裏付ける。
【ポイント3:個人事業主時代の証明方法】
過去に会社員ではなく、個人事業主として実務を積んでいた期間を証明する場合、特に注意が必要です。
- 確定申告書の写し(事業内容が建設業と分かるもの)
- 税務署の受付印がある書類
- 工事の契約書や請求書
これらを提出し、事業の実態と工事への従事状況を客観的に示さなければなりません。単なる領収書やメモでは認められにくいので、必ず公的な書類とセットで提出しましょう。
3. 実務経験の立証は「量より質」
多くの許可行政庁では、通常、証明しようとする期間(10年間)のうち、毎年の工事実績を数件提出することを求めてきます。契約書や請求書が大量にあれば良いわけではなく、「この人が、この期間に、間違いなくこの業種に従事した」と審査官が納得できるだけの、質と量のバランスが取れた資料の提出が求められます。
4|まとめ:実務経験での許可取得を成功させるために

「実務経験10年」を証明して建設業許可を取得することは、資格を保有している場合と比較して、手続きが格段に煩雑になります。
1. 許可取得へのロードマップ
- 自己の経験年数の確認: 申請したい業種について、本当に10年以上の実務経験があるか確認する。
- 証拠書類の収集・整理: 過去10年間の工事台帳、契約書、請求書、確定申告書などを、年ごとに整理する。
- 不足部分の確認: 証明に穴がある期間がないか、契約書などが紛失している部分がないかを確認する。
- 専門家への相談: 実務経験による証明は難易度が高いため、建設業許可専門の行政書士に相談し、証明可能な経験であるかの判断と書類作成のサポートを依頼する。
長年の経験があるにもかかわらず、許可の要件を満たせないというのは非常にもったいないことです。
「資格がないから」と諦めずに、まずはご自身の「実務経験」という財産を客観的な書類で証明できるかを検証することから始めてみましょう。



