知っておきたい河川法:許可が必要なケースから手続きまで徹底解説
知っておきたい河川法:許可が必要なケースから手続きまで徹底解説

「河川の近くで何かをしたいけど、勝手にやっていいのかな?」「河川法に抵触するなんてちらっと聞いたことがある…」
私たちの生活に身近な河川は、洪水や土砂崩れといった災害から国土を守り、安定した水の供給や環境保全の役割を担う重要な公共物です。そのため、河川の安全と機能を守るために「河川法」という法律で厳格に管理されています。
この法律を知らずに、安易に河川やその周辺で行動を起こしてしまうと、思わぬ事故や法律違反につながる可能性があります。この記事を読めば、河川法の基本から、どのような場合に許可が必要になるのか、そしてその手続き方法まで、初心者の方でも理解できるよう分かりやすくに解説します。これから河川の近くで何かを建設したりしようとしている方は必見です。
河川法とは?その目的と基本概念
河川法は、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的としています。この目的を達成するために、河川区域内での特定の行為を制限し、許可制度を設けています。
河川法の管理対象となる「河川」の種類
河川法が適用される河川には、主に以下の3つの種類があります。
- 一級河川: 国土の保全上特に重要な水系で、国土交通大臣が管理します。大規模な河川がこれに該当します。
- 二級河川: 一級水系以外の水系で、公共の利害に重要な関係があるものとして、都道府県知事が管理します。
- 準用河川: 一級・二級河川以外の小規模な河川で、市町村長が管理します。
- 普通河川: 地方公共団体が管理する河川です。
あなたが関わる河川がどの種類に該当するかは、管轄する地方自治体(都道府県や市町村の河川管理課など)のウェブサイトで確認することができます。(一部地域では窓口に問い合わせる必要があります。)
法律の適用範囲:河川区域と河川保全区域
河川法による規制は、主に「河川区域」と「河川保全区域」という2つのエリアで行われます。
- 河川区域: 河川の流水が常時存在している土地や、堤防、護岸といった河川管理施設、そしてその周辺で一体的に管理が必要と指定された区域を指します。いわゆる「川の中」や「堤防の上」がこれにあたります。
- 河川保全区域: 堤防の決壊や河岸の浸食を防ぐため、河川区域に隣接して指定される区域です。一般的に、堤防の端から20メートル以内(地域によって範囲が違う場合があります)の範囲が指定されることが多いです。
この2つの区域では、河川の安全や機能を損なう可能性のある行為が厳しく制限されます。
許可が必要となる主なケースとは?

「どんなことをしたら許可が必要なの?」という疑問は、多くの方が抱くものです。河川区域や河川保全区域で行う行為の中でも、特に河川の安全や環境に影響を与える可能性のあるものについては、河川管理者の許可が義務付けられています。
主な許可対象行為は以下のとおりです。
1. 工作物の新築・改築・除去(河川法第26条)
堤防や護岸、橋、電柱、水道管などのような構造物を河川区域内に新設・改築・撤去する際には許可が必要です。小規模なものであっても、安全を確保するためには事前の許可が不可欠です。
2. 土地の占用(河川法第24条)
河川区域内の土地を特定の目的で継続的に利用する場合、許可が必要です。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 運動場、公園、広場、駐車場などとして利用する場合
- イベント、祭り、撮影などで一時的に利用する場合
- 資材置き場、仮設事務所などを設ける場合
3. 土地の掘削・盛土・切土(河川法第27条)
河川区域内の土地の形状を変える行為は、水の流れや堤防の強度に影響を与えるため、許可が必要です。
- 土地を掘り下げる(掘削)
- 土を盛り上げる(盛土)
- 斜面を削る(切土)
4. 保全区域内の形状変更、工作物の新築・改築(河川法第55条)
河川保全区域内で土地の形状変更、工作物の新築等を行う場合に必要な許可です。
これら以外にも、河川の安全や環境を損なう恐れのある行為は、個別具体的に許可が必要となる場合があります。些細な行為でも「もしかして?」と感じたら、まずは管轄の河川管理事務所などに相談することが重要です。
罰則について:無許可での行為は絶対にNG!
「バレなければ大丈夫だろう」と安易に考えるのは非常に危険です。河川法に違反して無許可で行為を行うと、厳しい罰則が科せられます。
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
これらの罰則は、個人だけでなく、法人にも適用される場合があります。法律違反によって発生した損害は、すべて自己責任となり、原状回復のための費用も多額になります。法律を遵守することで、あなた自身の安全と財産を守りましょう。
河川法許可申請の手続きガイド

許可が必要な行為だと分かったら、次は申請の手続きです。手続きは煩雑に感じるかもしれませんが、流れを理解すればスムーズに進めることができます。
ステップ1:事前の相談・確認
いきなり申請書類を提出するのではなく、まずは管轄の河川管理者に事前に相談しましょう。これにより、計画内容が許可基準を満たしているか、必要な書類は何か、といった情報を事前に確認でき、手続きを効率的に進めることができます。
【相談時に準備しておきたいこと】
- 場所: どの河川のどの地点で、どのような行為をしたいか(地図や住所、地番など)
- 行為内容: 何を目的として、どのような工事や利用を計画しているか
- 時期: いつ頃から開始し、いつ頃完了予定か
ステップ2:必要書類の準備
相談内容に基づき、必要な書類を準備します。必要書類は行為の内容によって異なりますが、一般的には以下のものが求められます。
- 許可申請書: 所定の様式に必要事項を記入します。
- 事業計画概要書: 計画の目的、内容、工程などを詳しく説明します。
- 設計図、位置図、平面図、横断図、構造図: 計画場所や工作物の詳細な図面を準備します。
- 土地の権原を証する書類: 土地の所有者であることを証明する書類(登記簿謄本など)。
- 現況写真: 計画地の現状がわかる写真。
- その他: 他の行政機関の許可が必要な場合は、その許可書など。
これらの書類は、河川管理者が計画内容を審査するために非常に重要です。不備がないよう、丁寧に作成しましょう。
ステップ3:申請書の提出
書類がすべて揃ったら、管轄の河川管理者に提出します。提出方法は窓口に持参する、郵送、電子申請など、自治体によって異なりますので事前に確認しましょう。
ステップ4:審査
提出された申請書は、河川管理者によって内容が審査されます。審査では、主に以下の点が確認されます。
- 治水・利水上の支障がないか: 洪水時の水の流れや水利用に悪影響がないか。
- 河川環境や景観を損なわないか: 周辺の自然環境や美しさを守れるか。
- 安全性: 構造物の安全性が確保されているか。
審査には通常、数週間から数ヶ月かかることがあります。また、書類の不備があった場合は、補正を求められることもあります。
ステップ5:許可書の交付
審査が問題なく完了すると、許可書が交付されます。許可書には、工事の期間や方法、完了後の維持管理方法など、遵守すべき条件が記載されています。
ステップ6:工事着手・完了届
許可を得たら、工事に着手できます。工事着手前や完了後には、着手届や完了届の提出が義務付けられている場合が多いです。また、完了後の維持管理も許可条件に含まれていることがあります。
まとめ:河川法を理解し、安全な利用を
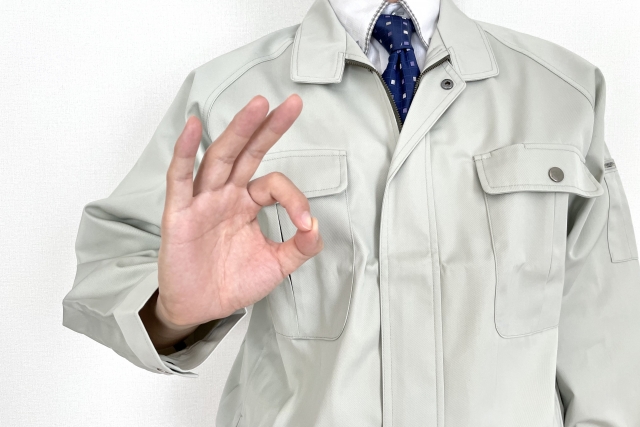
河川法は、私たちの安全と、かけがえのない自然を守るための大切な法律です。 「河川区域」や「河川保全区域」での行為は、たとえ小さなことでも許可が必要になるケースがあることを覚えておきましょう。
無許可での行為は、法律違反による罰則だけでなく、河川の氾濫や土砂崩れといった大きな災害を引き起こす原因にもなりかねません。計画段階で必ず役所や河川管理事務所等へ相談し、適切な手続きを踏むことが、あなた自身の安全と地域の安心につながります。
もし、「うちの土地は河川に面しているけど、許可が必要なのかな?」と少しでも不安に感じることがあれば、お近くの河川管理事務所や役所の河川担当部署に問い合わせてみましょう。
これから川の近くで何か事業等を始めようとしている方のお役に立てると幸いです。




市街化調整区域に宅地を造成するために国土交通省河川事務所に生活排水(集中合併浄化槽からの排水)を流すために行う許可申請は必要ですか?
地域水利組合からの申請になるのでしょうか。