【保存版】農地を駐車場や資材置き場に!農地転用許可申請の進め方
【保存版】農地を駐車場や資材置き場に!農地転用許可申請の進め方

農地の有効活用をするための、駐車場や資材置き場への転用は、土地の収益性を高める魅力的な選択肢です。しかし、この転用を実現するためには、農地法に基づく厳格な手続きが不可欠となります。この記事では、農地転用許可申請の経験がある方、あるいは既に基本的な知識をお持ちの方を対象に、より高度な視点から成功への道筋を解説します。単なる手続きの流れだけでなく、許可を得るための戦略や、見落としがちな落とし穴まで、解説します。
別記事:農地転用とは?
目次
農地転用許可申請の基本を再確認:なぜ許可が必要なのか?
農地転用は、農地法第4条(自己転用)または第5条(権利移動を伴う転用)に基づき、都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要です。この許可制度は、優良な農地の確保と計画的な土地利用を図るために設けられています。
【ポイント】
- 申請先と管轄: 申請先は原則として都道府県知事ですが、一部地域では農林水産大臣の許可が必要な場合があります。また、市区町村の農業委員会を経由して申請します。
- 市街化区域内の特例: 市街化区域内では、転用が比較的容易で、農業委員会への届出制が採用されています。ただし、この場合も農地法に基づく届出であり、要件を満たしているかどうかの審査は行われます。
申請手続きの流れとステップごとの注意点
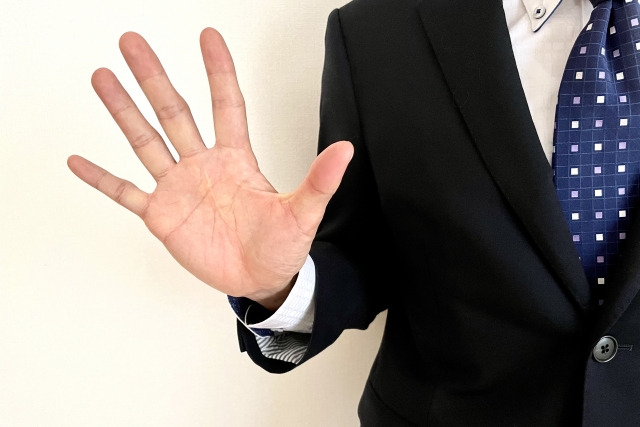
農地転用許可申請は、単に書類を提出すればよいというものではありません。事前の準備から許可後の手続きまで、各ステップで綿密な計画と対応が求められます。
ステップ1:事前の情報収集と関係各所との調整
転用を検討する段階で、まず行うべきは事前準備です。
- 農業委員会へ相談: 転用予定地の営農状況、周辺農地への影響などを確認します。
- 各自治体の都市計画担当課と相談: 転用予定地が都市計画法上のどの区域に位置するか、建築基準法上の制限、その他条例などを確認します。
- インフラ管理者と相談: 上下水道、電気、ガスなどのインフラ整備が必要な場合、各事業者の事前相談は必須です。
【戦略】 この段階で、転用計画の実現可能性を事前に把握し、潜在的な問題を洗い出しておくことが、後の手続きをスムーズに進める鍵となります。
ステップ2:必要書類の収集と作成
申請書類は多岐にわたり、一つでも不備があると審査が滞ります。特に注意が必要な書類は以下の通りです。
- 住民票抄本(譲受人または譲渡人が市外居住者の場合)
- 法人登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 土地の全部事項証明書
- 土地改良区意見書等 別記事:土地改良区の概要
- 資金証明書
- 公図
- 土地利用計画図
- 建物等平面図
- 排水同意書
- 道水路占用等許可書
- 資格証明書
- 事業計画書
- 位置図
- 案内図
- 委任状
- 確認書
- 農地復元計画書
- その他参考となるべき書
【専門的アドバイス】
- 資金計画の具体性: 預金通帳のコピーなど、具体的な証拠が必要です。
- 排水計画の説得力: 雨水が適切に排水されることを、図面と文章で詳細に説明します。特に隣接する農地への影響は厳しく審査されます。
ステップ3:農業委員会への申請と審査
提出された書類は、まず農業委員会で審査されます。
- 現地調査: 農業委員会の委員が現地を訪れ、書類の内容と実際の状況に相違がないかを確認します。
- 定例総会での審議: 農業委員会定例総会で、申請内容が審議されます。ここで反対意見が出されることもあり、事前の協議が重要となります。
- 都道府県への送付: 農業委員会での審査を経て、許可相当と判断された場合、書類は都道府県へ送付されます。
【注意点】
- 現地調査への対応: 質問に対して明確かつ誠実に回答できるよう、転用計画をしっかりと頭に入れておきましょう。
- 農地転用に関する意見書の提出: 農業委員会が開催する総会で、利害関係者からの意見書が提出されることがあります。
ステップ4:都道府県での審査と許可
都道府県では、農地法第4条・第5条の許可基準に基づき、最終的な審査が行われます。
- 立地基準: 転用予定地が、市街化調整区域内の優良農地(農用地区域内農地、第1種農地など)に該当しないかなどを審査します。
- 一般基準: 転用計画が確実に行われるか、周辺農地に悪影響を及ぼさないか、資金計画が妥当かなどを審査します。
【専門的視点】
- 立地基準のクリア: 優良農地での転用は原則不許可です。事前に農地区分(甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地)を確認することが不可欠です。
駐車場・資材置き場への転用で特に注意すべきポイント
一般的な転用と異なり、駐車場や資材置き場への転用には、特有の注意点があります。
- 事業計画の具体性:
- 駐車場の転用であれば、利用台数、利用料金、運営方法などを具体的に記述します。
- 資材置き場であれば、保管する資材の種類、搬入・搬出方法などを詳細に記載します。
- 工事計画の明確化:
- 転用後の土地利用形態(アスファルト舗装、砕石敷き、フェンス設置など)を明確にします。
- 工事の進捗スケジュール、具体的な工法などを図面と共に示します。
- 騒音・振動対策:
- 資材置き場の場合、重機や大型車両の出入りによる騒音・振動が問題となる可能性があります。近隣住民への配慮や対策を事業計画に盛り込むことで、審査が円滑に進む場合があります。
許可後の手続きと厳守事項
農地転用許可はゴールではありません。許可取得後も、以下の手続きが求められます。
- 工事着手届・完了届の提出: 工事の進捗状況を農業委員会に報告します。
- 地目変更登記: 転用後、土地の地目を「田」や「畑」から「宅地」などに変更するための登記手続きを行います。これは土地家屋調査士に依頼することも可能です。
【重要】 許可を得た後、転用目的や計画を変更する場合、計画変更申請が必要となるケースがあります。無許可で転用を進めると、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となるため、厳重な注意が必要です。
まとめ:成功への戦略的アプローチ

農地転用許可申請は、単に手続きをこなすだけでなく、戦略的なアプローチが求められます。
- 事前の情報収集と関係各所への相談。
- 申請書類は、専門家の視点から見て説得力のある内容に仕上げる。
- 転用目的(駐車場・資材置き場)に特化した詳細な計画を立てる。
これらのポイントを押さえることで、あなたの農地転用計画はよりスムーズに、そして確実に実現へと向かうでしょう。
どうしても行き詰ってしまったら、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。




“【保存版】農地を駐車場や資材置き場に!農地転用許可申請の進め方” に対して1件のコメントがあります。