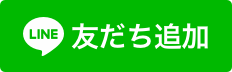【非農地証明とは】農地転用が不要になる?デメリットはあるの?行政書士が解説!
【非農地証明とは】農地転用が不要になる?デメリットはあるの?行政書士が解説!

農地転用を検討中の方へ。土地が「どう見ても農地じゃない」と思える状態の場合、非農地証明という手続きを利用することで、農地転用の手続きが不要になる可能性があります。
この記事では、非農地証明の概要、農地転用との関係、メリット・デメリット、申請の流れについて、行政書士の視点から詳しく解説します。
目次
1|非農地証明とは?農地転用との決定的な違い

1. 農地と「非農地」の定義
農地とは、法律(農地法)上、「耕作の目的に供される土地」を指します。たとえ現在耕作されていなくても、いつでも耕作が可能な状態にある土地も含まれる場合があります。農地の売買や、農地を農地以外の目的(住宅、駐車場など)に利用する行為は、原則として農地法に基づく都道府県知事の許可(農地転用許可)が必要です。
一方、非農地とは、その名の通り、農地法の適用を受けない土地を指します。
2. 非農地証明の役割
非農地証明とは、市町村の農業委員会が、特定の土地が「農地法の適用を受ける農地ではない」ことを公的に証明するものです。
具体的には、長期間にわたり耕作が放棄され、森林化している、宅地化が進んでいる、あるいは河川の一部として使われているなど、物理的な状況や利用状況から見て、将来にわたっても農地として再生・利用することが極めて困難と認められる場合に発行されます。
この証明書が発行されれば、その土地は法律上「農地」ではなくなるため、農地を農地以外のものにするための「農地転用」手続き(許可申請)が不要になります。
3. 農地転用との決定的な違い
| 項目 | 非農地証明 | 農地転用許可(例:農地法第4条・第5条) |
| 目的 | その土地が法律上「農地ではない」ことを証明すること | 農地を農地以外の目的に変えることの許可を得ること |
| 対象土地 | 既に農地としての機能を失っている土地 | 現在は農地であり、これから目的を変えたい土地 |
| 審査基準 | 土地の現在の物理的な状態と耕作不能の恒久性 | 計画の妥当性、立地基準(優良農地の保全)、転用の必要性 |
| 効果 | 農地法の適用から外れる(転用手続き不要) | 農地法の適用内で、目的変更が許可される |
ポイント: 非農地証明は、「農地を転用する」行為そのものを省略させるのではなく、「その土地はそもそも農地ではない」と認定してもらう手続きなのです。
別記事:【保存版】農地を駐車場や資材置き場に!農地転用許可申請の進め方
2|非農地証明を取得できるのはどんな土地?

非農地証明の要件は、各市町村の農業委員会によって若干の差がありますが、一般的には以下のいずれかに該当し、かつ農地として再生することが困難であると認められる必要があります。
1. 長期間耕作放棄され、非農地化している土地
「どう見ても農地じゃない」土地の典型例です。
- 長期間(概ね10年以上)、耕作が行われていないこと。
典型例:
- 樹木の繁茂・森林化: 木が生い茂り、森林法上の林地と見なせる状態。
- 永続的な施設の存在: 土地の一部または全部に、コンクリート構造物、資材置場、廃墟などが長期間存在し、農地に戻すのが著しく困難な状態。
- 自然的な浸食・損壊: 土砂崩れ、河川の浸食、または湿地化により、客観的に見て復元が著しく困難な状態。
2. 農地法施行以前からの農地以外の土地
農地法施行(昭和27年10月21日)以前より、農地ではない土地(宅地等)であった土地も非農地証明の取得が認められます。
3. 発行の可否は農業委員会の判断次第
非農地であるかどうかの判断は、農業委員会の現地調査に基づき、その裁量によって行われます。要件に合致しているかどうかは、写真、公図、航空写真、および周辺状況など、客観的な証拠を基に厳しく審査されます。
「木が生い茂っているから大丈夫だろう」と自己判断せず、必ず事前に農業委員会や行政書士に相談しましょう。
3|非農地証明のメリットとデメリット

非農地証明を取得することは、土地利用を考える上で非常に大きな利点がありますが、一方で留意すべき点もあります。
1. 非農地証明を取得するメリット
1. 農地転用手続きが不要になる
最大のメリットです。通常、農地転用許可を得るには、手続きが非常に煩雑で時間と費用がかかります。非農地証明が取得できれば、この複雑な手続きと時間的制約から解放されます。
2. 土地利用の自由度が格段に上がる
農地法の規制から外れるため、宅地、駐車場、資材置場など、非農地としての利用が自由になります。特に、市街化調整区域などの開発が厳しく規制される地域では、この自由度は非常に価値があります。
3. 資産価値の向上と円滑な売買
農地法の規制が外れることで、土地の買い手が増え、円滑な売買が可能になります。買い手側も、農地転用のリスクや時間を考慮する必要がなくなるため、土地の資産価値が向上する可能性があります。
4. 登記地目の変更の根拠になる
非農地証明は、土地の登記地目(田、畑)を雑種地や宅地などに変更するための法的な根拠の一つとなります。
2. 非農地証明のデメリット・注意点
1. 取得が難しい(ハードルが高い)
農業委員会は優良農地の保全を使命としています。そのため、「少し手を加えれば農地に戻せる」と判断される土地には、基本的に非農地証明は発行されません。証明取得には、恒久的な非農地化の強固な証拠が必要です。
2. 計画的な転用には利用できない
非農地証明は、「既に非農地化している事実」を証明するものであり、「これから農地を変える」という計画的な転用には使えません。
3. 取得後も法的な規制が残る場合がある
非農地証明を取得しても、都市計画法(開発許可)、建築基準法、森林法、砂防法など、他の法律による規制はそのまま残ります。証明取得後も、新たな建築行為などを行う際は、それらの法律に基づいた手続きが必要です。
4. 固定資産税が高くなる可能性がある
地目が「田」や「畑」である農地は、一般的に固定資産税の評価額が低く抑えられています。非農地証明を取得し、地目を「雑種地」や「宅地」に変更すると、土地の評価額が上がり、固定資産税が増額する可能性があります。これは土地の利用目的や地域の状況によりますが、事前に試算が必要です。
4|非農地証明の申請手続きの流れ

非農地証明の申請は、一般的に以下の流れで進めます。
Step 1. 事前相談と現地調査
まず、土地の所在地を管轄する市町村の農業委員会に相談します。非農地証明の要件、必要な書類、現地調査の時期などを確認します。この際、現状の写真を提示するなどして、非農地化の状況を具体的に説明することが重要です。
Step 2. 必要書類の準備
農業委員会の指示に従い、以下の書類を準備します。
- 非農地証明交付願(所定の様式)
- 土地登記事項証明書
- 公図の写し
- 現況写真
- 位置図
一般的には、これらの書類が必要になります。自治体によって異なるため、必ず事前にお住いの市町村の農業委員会に問い合わせてください。
Step 3. 申請書の提出
準備した書類一式を、農業委員会に提出します。
Step 4. 農業委員会による現地調査
農業委員会の職員が実際に現地を訪れ、申請内容と土地の状況が一致しているか、農地として再生することが本当に困難であるかを厳しく確認します。
Step 5. 審査と証明書の交付
現地調査の結果や提出された証拠に基づき、農業委員会総会などで審査が行われます。非農地と認められた場合、申請者に対して通知書が交付されます。
5|行政書士が解説する成功へのヒント

非農地証明は、単なる申請手続きではなく、「この土地が恒久的に農地ではない」という法的事実を、説得力ある証拠をもって証明する行為です。
1. 現地調査対策は入念に
農業委員会は、申請者が意図的に農地を荒廃させた(作為的な荒廃)のではないかという点を厳しくチェックします。証明申請直前に急いで木を植えたり、建物を壊したりすると、かえって疑念を抱かせることになります。
行政書士は、非農地化の状況を正確に把握し、客観的な証拠(特に長期的な非農地化を示す資料)を揃えることで、作為的な荒廃ではないことを論理的に説明するサポートが可能です。
2. 法的規制を事前に把握する
非農地証明を取得できたとしても、地目変更や建築行為には都市計画法や建築基準法などの手続きが別途必要です。
行政書士は、これらの関連法規も含めた全体的な土地利用の計画を立てるサポートをします。
3. 固定資産税の試算を忘れずに
前述の通り、固定資産税が増額するリスクがあります。非農地証明を取得する前に、地目変更後の税額の目安を関係機関で確認し、トータルで見た場合の経済的なメリット・デメリットを把握することが賢明です。
6|まとめ
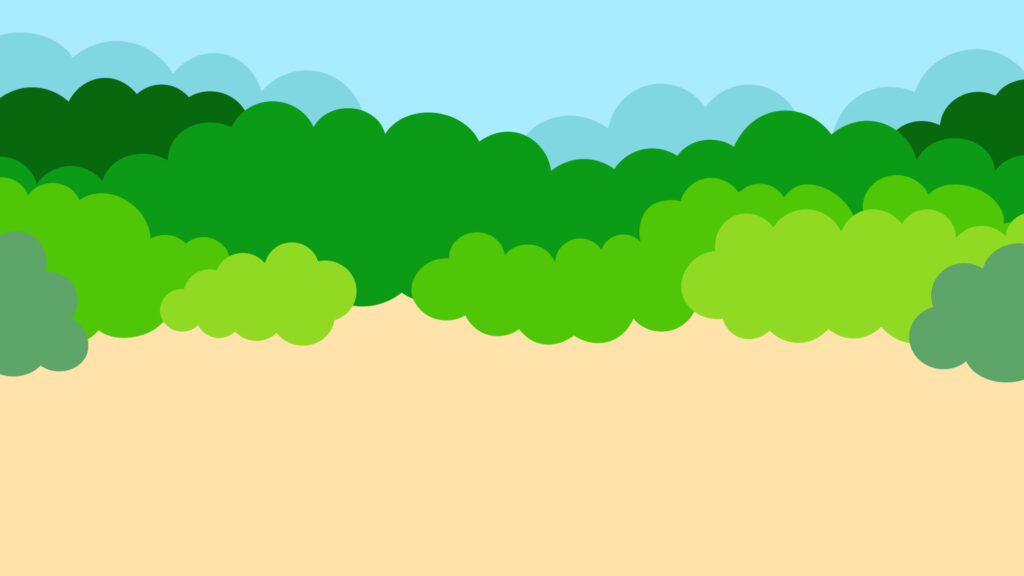
木が生い茂り、どう見ても農地としての機能を失っている土地をお持ちの場合、非農地証明は、煩雑な農地転用許可手続きを回避し、土地利用の自由度を高める非常に有効な手段です。
しかし、その取得には長期にわたる非農地化の明確な証拠が必要であり、審査のハードルは決して低くありません。
非農地証明の申請を検討される際は、専門知識を持つ行政書士にご相談ください。現地調査への対応、必要な客観的証拠の収集、書類作成を通じて、スムーズで確実な手続きをサポートいたします。
弊所のご紹介
弊所は各種許認可に特化した行政書士事務所です。
非農地証明申請はもちろん、農地転用許可も取扱っております。ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。公式ラインからでも大歓迎です。