【建築士事務所登録】登録に必要な要件を行政書士が解説!不要な場合は?
【建築士事務所登録】登録に必要な要件を行政書士が解説!不要な場合は?

これから建築設計・工事監理の業務を本格的に始めようと考えている方へ。
「建築士事務所登録って必要なの?」「どんな要件を満たせば登録できるの?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
建築士として、設計や工事監理の報酬を得て業務を行うためには、「建築士事務所の登録」が必要不可欠です。しかし、この手続きは複雑で、「自分は登録が必要なのか」と迷われる方も少なくありません。
この記事では、専門家である行政書士が、登録が必要なケース・不要なケース、そして登録に必要な要件や手続きの流れを、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。
これから建築士事務所登録をお考えの方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
090-9451-9906(茂木)
1|建築士事務所登録とは?なぜ必要なのか

1. 建築士事務所登録の目的と法律的根拠
「建築士事務所登録」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士の資格を持つ者が、他者の求めに応じて、報酬を得て建築物の設計、工事監理等の業務を行うために、建築士法に基づき行うことが義務付けられている登録制度です。
この制度の主な目的は、設計・工事監理業務の適正化と、建築主(依頼者)の保護です。
建築士法第23条では、「建築士事務所の開設者は、その建築士事務所について、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」と定められており、登録をせずに業務を行うことは法律違反となります。
2. 登録が必要な「業務」の範囲
建築士事務所の登録が必要となる業務とは、具体的に以下のものが挙げられます。
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務(積算業務、入札補助など)
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査または鑑定
- 建築に関する法令または条例に基づく手続きの代行
このうち、特に重要なのが「設計」と「工事監理」です。これらの業務を有償(報酬を得て)行う場合、建築士事務所の登録は必須となります。
2|【重要】あなたの場合は必要?不要?判断の基準

「自分は建築士の資格を持っているけど、登録が必要なのか分からない…」という方も多いはず。ここでは、登録が必要なケースと、例外的に不要となるケースを明確に解説します。
1. 建築士事務所登録が「必要」なケース
建築士事務所登録が必須となるのは、「報酬を得て、他者のための設計または工事監理を行う」場合です。
| 対象者 | 具体的な業務例 | 登録の必要性 |
| 独立開業する建築士 | 建築主からの依頼を受け、住宅やビルなどの設計・監理を行う。 | 必須 |
| 設計部門を持つ建設会社 | 自社で元請として設計・施工を一貫して行う場合でも、設計業務には登録が必要。 | 必須 |
| フリーランスの建築士 | 他の事務所や会社から業務委託を受け、設計・監理を行う。(業務委託料が報酬にあたる) | 必須 |
【ポイント】
報酬の有無、依頼主が他人であるかどうかが最大の判断基準です。たとえ小規模な案件であっても、対価を得て設計・監理を行うなら登録は必要です。
090-9451-9906(茂木)
2. 建築士事務所登録が「不要」なケース(例外)
以下のいずれかに該当する場合は、建築士事務所の登録は不要です。
(1) 資格はあっても設計・監理を業務として行わない場合
- 建築士資格を利用しない職務:
- 建築関連法規のコンサルタントのみを行う。
- 建築材料の研究、販売のみを行う。
- 建設業の現場監督のみを行う(設計・監理を行わない)。
(2) 自社の建物のみの設計・監理を行う場合
- 社内建築士が、勤務先の自社所有の建物(例:自社ビル、工場など)の設計・監理のみを行う場合。
- これは「他者の求めに応じて」報酬を得る行為ではないため、登録は不要です。
- ただし、親会社やグループ会社の建物を設計・監理する場合は、原則として登録が必要です(他者とみなされるため)。
(3) 報酬を得ないで設計・監理を行う場合
- ボランティアや趣味の範囲で、完全に無償で知人の建物の設計・監理を行う場合。
- ただし、無償であることを明確にする書類がないと、後でトラブルになる可能性があるため注意が必要です。
3|建築士事務所登録の「5つの必須要件」
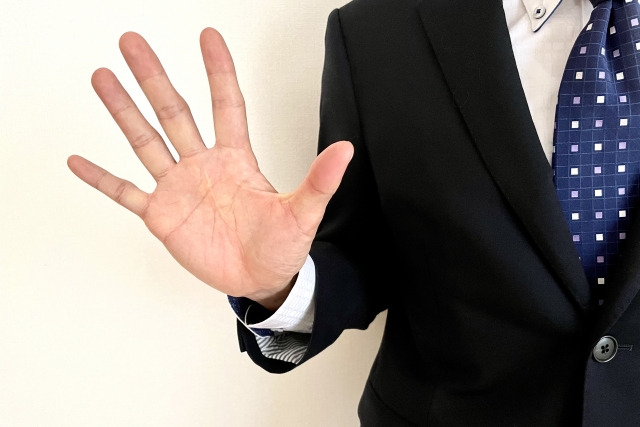
建築士事務所の登録をするためには、建築士法に基づき、以下の5つの要件をすべて満たしている必要があります。
1. 要件1:管理建築士の設置
建築士事務所には、その業務を統括する「管理建築士」を1名置かなければなりません。また、管理建築士は常勤でなければなりません。
- 管理建築士の資格要件:
- 登録しようとする事務所の種別に対応する建築士(一級、二級、または木造建築士)であること。
- 建築士として3年以上の設計等業務に従事した後、管理建築士講習を修了していること。
「3年以上の実務経験」と「管理建築士講習の修了」は、必ず満たさなければならない重要な要件です。
2. 要件2:事務所の名称
事務所の名称には、「建築士事務所」等の建築士事務所だと分かるような文字を含めなければなりません。
(例:○○一級建築士事務所、△△デザイン建築士事務所など)
3. 要件3:事務所の所在地(場所)
建築士事務所として適正に業務を行える場所を確保する必要があります。
- 注意点:
- 自宅兼事務所の場合、居住スペースと業務スペースが明確に区別できているかどうかが審査されることがあります。
4. 要件4:欠格事由に該当しないこと
建築士事務所を開設しようとする人(法人であれば役員全員)が、建築士法第26条に定められた欠格事由に該当しないことが必要です。
- 主な欠格事由:
- 建築士法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 事務所登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。
- 成年被後見人、被保佐人。
5. 要件5:登録手数料の納付
登録申請時に、各都道府県が定める手数料(法定費用)を納付する必要があります。手数料は都道府県によってさまざまのため、お住いの都道府県のウェブサイトを確認してください。
090-9451-9906(茂木)
4|建築士事務所登録の種類と必要な建築士資格

建築士事務所の登録は、取り扱う建築物の規模や構造に応じて、3つの種類に分かれています。
| 事務所の種類 | 業務として行える設計・監理の範囲 | 必要な建築士資格 |
| 一級建築士事務所 | 全ての建築物 | 一級建築士 |
| 二級建築士事務所 | 二級建築士が扱える建築物(主に戸建住宅など比較的小規模なもの) | 二級建築士 |
| 木造建築士事務所 | 木造建築士が扱える木造建築物 | 木造建築士 |
あなたが今後どのような建築物を主に扱っていくかによって、どの種類の事務所として登録するかが決まります。一級建築士事務所として登録すれば、全ての設計・監理を行うことが可能です。
5|建築士事務所登録の手続きの流れと必要書類

登録手続きは、事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行います。
1. 標準的な手続きの流れ
- 管理建築士講習の受講・修了:管理建築士となる人が受講を完了します。
- 必要書類の準備:後述の書類を収集・作成します。
- 登録申請書の提出:都道府県の窓口(または所定の団体)に提出します。
- 審査:申請内容に不備がないか、要件を満たしているかが審査されます。
- 登録の実施と通知:登録が完了すると、登録簿に記載され、開設者に通知されます。
- 事務所の業務開始:通知を受けた後、業務を開始できます。
2. 主な必要書類(群馬県の場合)※自治体により異なる場合があります
- 建築士事務所登録申請書
- 建築士事務所登録添付書類(業務概要書・略歴書・誓約書)
- 管理建築士の資格証明書(建築士免許証の写し)
- 管理建築士講習修了証の写し
- 登録申請者が法人である場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)・定款の写し
- 所属建築士の名簿
- 役員名簿
【ワンポイントアドバイス】
特に「管理建築士の実務経験証明」など、添付書類の作成・収集は時間がかかる場合があります。余裕を持って準備を開始しましょう。
090-9451-9906(茂木)
6|登録後の義務と注意点

登録が完了して終わりではありません。建築士事務所には、建築士法に基づく様々な義務が課せられます。
1. 登録の有効期間と更新手続き
建築士事務所の登録は、永久的なものではありません。
- 有効期間:5年間
有効期間満了後も業務を継続する場合は、期間満了の30日前までに更新の申請を行う必要があります。更新時にも、管理建築士の要件などが再確認されます。
2. 帳簿の備え付けと業務報告
開設者は、設計・工事監理の業務ごとに、業務に関する事項を記載した帳簿を作成し、事務所に備え付けておかなければなりません(15年間保存義務)。
また、毎年一度、事業年度ごとに業務報告書を作成し、都道府県知事に提出することが義務付けられています。
3. 標識の掲示義務
事務所の外部から見やすい場所に、定められた様式・内容の標識(登録票)を掲示しなければなりません。
7|まとめ:スムーズな登録のために行政書士をご活用ください

建築士事務所登録は、あなたが建築士として社会に貢献し、合法的に報酬を得て業務を行うための、いわば「スタートライン」です。
- 報酬を得て、他人の設計・工事監理を行うなら「登録は必須」
- 「管理建築士の設置」と「3年以上の実務経験+講習修了」が重要要件
- 登録後も「5年ごとの更新」と「業務報告」の義務がある
書類の準備や法的な要件の確認は、煩雑で専門知識を要します。
「自分は要件を満たしているか?」「書類の書き方が分からない」といった不安がある方は、専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士は、必要書類の作成・収集から、行政庁への申請代行まで、すべてをサポートいたします。お客様は本業である建築の仕事に集中していただくことが可能です。
建築士としての新たな一歩を、私たち専門家と共に、確実でスムーズなものにしましょう。
090-9451-9906(茂木)
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
建設業許可はもちろん、建築士事務所登録も取扱っております。ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。



