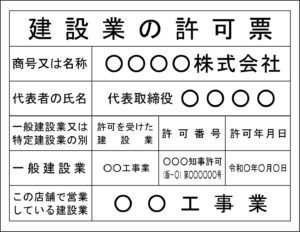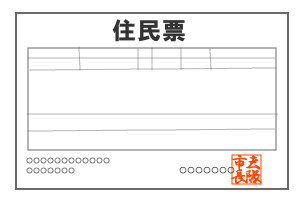【埋蔵文化財包蔵地】知らずに工事を行うと一大事!概要と確実に調べる方法を行政書士が解説
【埋蔵文化財包蔵地】知らずに工事を行うと一大事!概要と確実に調べる方法を行政書士が解説

新築住宅の建設、アパート・マンションの造成、太陽光発電設備の設置、または駐車場整備など、土地に手を加える工事を計画されている皆様。
工事計画を立てる際、「建築基準法」や「都市計画法」に基づく手続きは念入りに進めるかと思いますが、もう一つ、絶対に確認を怠ってはいけない重要な手続きがあります。それが、埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)に関する調査と届出です。
もし、ご自身の土地がこの「埋蔵文化財包蔵地」に該当することを知らずに工事を始めてしまうと、工事の中断、計画の白紙撤回、想定外の費用負担といった「一大事」を招きかねません。
この記事では、各種許認可手続きをサポートする行政書士の視点から、埋蔵文化財包蔵地の重要性、工事前に確実に調査する方法、そして法律に基づく正しい手続きについて、分かりやすく徹底的に解説します。
目次
1|そもそも「埋蔵文化財包蔵地」とは?なぜ行政手続きが必要なのか
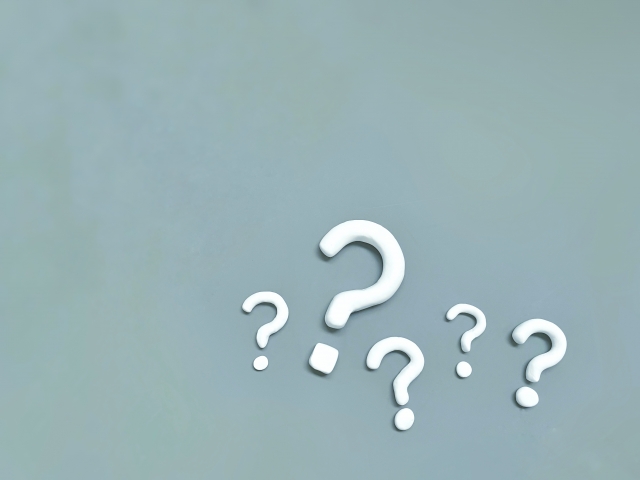
1. 文化財保護法が定める「遺跡が内包される土地」
埋蔵文化財包蔵地とは、その名の通り、「埋蔵文化財(遺跡や遺物)が内包されていることが、すでに知られている土地の範囲」を指します。いわゆる「遺跡」や「貝塚」などとして地図上に設定されているエリアのことです。
これらの地下に眠る土器、石器、住居跡などは、国民共有の貴重な歴史的・文化的財産であり、文化財保護法という法律によって厳重に守られています。
2. 法律上の義務と行政書士の役割
文化財保護法では、この「周知の埋蔵文化財包蔵地」において、建築や土木など、土の掘削を伴う工事を行う場合、着工の60日前までに教育委員会へ届け出ることを義務付けています(法第93条)。
これは、工事によって貴重な文化財が破壊されてしまうことを未然に防ぎ、必要に応じて事前に調査を行うための行政手続きです。
我々行政書士は、開発事業における各種許認可(農地転用、開発許可など)を扱う中で、この埋蔵文化財に関する届出も非常に重要な「関連手続き」として位置づけ、お客様の工事がスムーズに進むよう、事前調査から届出までをサポートしています。
2|知らずに工事を行うと発生する4つの重大リスク

「自分の土地なのだから、何をしても自由ではないか」と思われるかもしれませんが、地下に眠る文化財は公共の財産です。埋蔵文化財包蔵地での手続きを怠った場合、事業者に降りかかるリスクは甚大です。
リスク1:工事の即時中断と法律違反
工事中に土器の破片や昔の遺構の一部を発見した場合、たとえそれが包蔵地外であっても、直ちに工事を中断し、現状を変更せず、文化庁長官へ届け出ることが法律で義務付けられています(法第96条)。
この届出義務を怠り、文化財を破壊した場合は、文化財保護法に基づく罰則の対象となる可能性があります。
リスク2:多額の「発掘調査費用」の負担
事前の届出や試掘調査を経ずに工事中に文化財が発見され、その遺跡の価値が高いと判断された場合、工事は長期的に中断され、本格的な「発掘調査」が実施されます。
原則として、この発掘調査にかかる費用は、開発事業者が負担することになります。費用は土地の面積や遺跡の深さによって異なりますが、文化庁による調査費用の平均は94万円です(平成29年度)。場合によっては数百万単位の費用が発生する事例も少なくありません。
※事前に行う試掘調査の費用に関しては、原則として自治体に負担してもらえます。(例外あり)
リスク3:工期の大幅な遅延と機会損失
発掘調査は、規模に応じて数ヶ月に及ぶことが多いです。この間、事業は完全にストップするため、資金計画の狂い、契約違反、そして計画していた売上や収益の機会損失に直結します。
また、発掘調査の着手に至るまで時間がかかり、トータルで1年以上調査にかかる場合もあります。
特に、太陽光発電のようにFIT制度の認定期限が関わる事業においては、この遅延が致命傷になることもあります。
リスク4:工事計画の抜本的な見直し・中止
極めて重要な遺跡が発見された場合、教育委員会や文化庁は、その遺跡の現状保存を最優先するよう求めます。その結果、工事計画の抜本的な変更(設計の変更、建築範囲の縮小)、あるいは開発計画そのものの白紙撤回を余儀なくされる可能性もあります。
3|行政書士が教える!埋蔵文化財の有無を確実に調べる方法

このような重大リスクを避けるためには、工事の着手前に「埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかを確実に、正式な方法で調査することが不可欠です。
確実な調査は、次の2ステップで進めます。
Step 1:地図(台帳)調査 ・自治体の教育委員会への確認
まず最初に行うべきは、工事予定地が既に設定されている「周知の埋蔵文化財包蔵地」のエリア内にあるかどうかを確認することです。
確認先:市区町村の教育委員会
この情報は、各自治体の教育委員会、特に文化財保護課などで管理されています。
- 窓口または電話での確認: 工事予定地の正確な地番を伝え、「埋蔵文化財包蔵地のエリアに入っているか」を問い合わせます。
- インターネットでの確認: 近年は多くの自治体が「埋蔵文化財包蔵地マップ」や「遺跡地図」をインターネット上で公開しています。「[市区町村名] 埋蔵文化財包蔵地 マップ」で検索し、工事予定地がどの範囲に入るかを確認します。
※群馬県では【マッピングぐんま「遺跡・文化財」】というウェブサイトがあります。群馬県にお住いの方は下記リンク(外部リンク)からご確認ください。
【マッピングぐんま「遺跡・文化財」】:https://www2.wagmap.jp/pref-gunma/Portal
調査結果の見方と対応
- ① 包蔵地の「範囲内」: 届出・通知が必須です。工事着手の60日前までに手続きを開始してください。
- ② 包蔵地の「隣接地・周辺地」: 遺跡の範囲が広がる可能性があるため、自治体から試掘調査を推奨される場合があります。
稀に、包蔵地の範囲外でも試掘調査を推奨される場合もあるため、注意が必要です。
Step 2:現地調査 — 試掘調査(予備調査)の実施
地図調査で「包蔵地の範囲内」と判明した場合、または隣接地や過去に遺跡が出た土地で開発を行う場合は、通常、教育委員会から試掘調査(しくつちょうさ)の実施が提案されます。
試掘調査とは?
これは、工事予定地の数カ所を実際に重機などで試し掘りし、文化財の有無、存在深度、分布範囲を特定するための予備的な調査です。
この調査結果をもって、教育委員会が「本格的な発掘調査が必要か」、「工事の立会いだけで済むか」を判断する、最も重要なプロセスとなります。
試掘調査の費用と期間
- 費用: 前述の通り、多くの自治体で試掘調査は公費(無料)で実施されていますが、自治体の方針や調査の目的によっては事業者が一部費用を負担する場合もあるため、必ず事前に確認が必要です。
- 期間: 調査自体は数日で完了することが多いです。
4|埋蔵文化財包蔵地での行政手続きの具体的な流れ

試掘調査の結果、本格的な発掘調査が必要ないと判断された場合は、そのまま工事に着手できるケースが多いです。以下のような流れで進めていきます。
1. 【着工60日前】届出書の提出と事前協議
「埋蔵文化財発掘の届出」(法第93条)を行います。
2. 教育委員会の「指示」の受領
届出を受けて、教育委員会は以下のいずれかの「指示」を事業者に通知します。
- ① 慎重工事の依頼: 遺跡への影響が軽微な場合。
- ② 工事立会いの依頼: 遺跡を傷つけないよう、職員が立ち会う。
- ③ 発掘調査の要請: 遺跡の価値が高く、本格的な調査が必要な場合。
3. 発掘調査の実施と費用負担(パターン③の場合)
発掘調査が要請された場合、原則として事業者が費用を負担し、教育委員会等の専門機関が調査を実施します。この調査が終了し、文化財の記録保存が完了するまで、工事はできません。
ただ、営利目的ではない場合は(自己専用住宅建設等)補助制度もあるため、対象かどうか事前に確認をしておきましょう。
4. 調査完了後の工事再開
発掘調査の終了後、工事の再開が許可されます。
5|行政書士からのアドバイス:早期対応がすべてを解決する

埋蔵文化財包蔵地に関する手続きで最も重要なのは、「早期対応」です。
工事着工の直前になって包蔵地であることが判明すると、60日前ルールがあるために着工自体が大幅に遅れます。さらに、試掘調査や発掘調査が必要になった場合、資金計画や契約関係に深刻な影響を及ぼします。
許認可のプロフェッショナルである行政書士は、各種許可申請と並行して、埋蔵文化財の調査・届出を早期に組み込むことで、お客様の事業リスクを最小限に抑えるサポートをいたします。
工事計画が固まり次第、まずは土地の地番を持って教育委員会に問い合わせる。この一歩こそが、あなたの事業を「一大事」から守る、最も確実な対策となります。
また、文化財保護法だけではなく、その他関係法令に該当しないかのチェックも非常に重要です。工事が始まってから、他の法令に抵触することが判明したとなれば、工期の大幅な遅れ等の多大な損害が発生するため、法令確認は最重要ステップです。
【関係法令(例)】
- 河川法:別記事(知っておきたい河川法:許可が必要なケースから手続きまで徹底解説)
- 砂防法:別記事(【砂防法】砂防指定地とはどんな地域を指すの?調べる方法も解説!)
- 農地法:別記事(「農地転用」ってなに?基本から手続きまで、初めてでもわかる解説ガイド)
6|埋蔵文化財に関するQ&A(よくある質問)

Q1. 埋蔵文化財包蔵地内の土地でも、絶対に家や建物は建てられないのでしょうか?
A. 建てられないわけではありません。
重要なのは「遺跡の破壊を避けること」です。遺跡は地表からある程度の深さに存在することが多いため、掘削が浅く済む工事(例:地表に近い基礎、盛土を主とした工事)であれば、多くの場合、工事の立会いや慎重な工事で済ませることができます。重要なのは、「事前の確認・行政との協議」です。
Q2. 土地を購入する前に、埋蔵文化財包蔵地かどうかを調べることはできますか?
A. はい、できます。
むしろ、土地購入前に調べることを強く推奨します。不動産取引においては、宅地建物取引業者が重要事項説明で「埋蔵文化財包蔵地」である旨を説明する義務がありますが、ご自身でも、購入を検討している段階で自治体の教育委員会に地番を伝えて確認できます。
Q3. 届出は誰が行う必要がありますか?
A. 届出義務者は「土地を掘削する工事の主体者(事業主)」です。
土地の所有者自身が工事を行う場合は所有者、ハウスメーカーのどのが事業主体の場合はその会社が届出義務者となります。ただし、行政書士などの専門家が代理で届出書の作成や提出をサポートすることは可能です。
弊所のご紹介
弊所は各種許認可に特化した行政書士事務所です。
開発許可、農地転用許可も取扱っております。ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。