建設業許可があれば電気工事業登録は不要?両者の条件と違いとは
建設業許可があれば電気工事業登録は不要?両者の条件と違いとは

電気工事業を営む上で、必ずと言っていいほど直面するのが「建設業許可」と「電気工事業登録」という二つの制度です。特に、すでに建設業許可を持っている事業者の方や、これから両方の取得を検討している方の中には、「建設業許可があれば、わざわざ電気工事業登録はしなくてもいいのでは?」と疑問に思う方も少なくありません。
結論から言うと、建設業許可を持っていても、ほとんどの場合で電気工事業登録も必要となります。
この記事では、電気工事業登録と建設業許可の違い、それぞれの取得条件、そしてなぜ両方が必要なのかを、事業者の方が抱える疑問に答える形で詳しく解説していきます。
※建設業許可における電気工事業に関しては別記事で解説をしておりますのでこちらをご覧ください。
目次
1:電気工事業登録と建設業許可、目的と法律が全く違う!
まず、この二つの制度が全く異なる法律に基づいており、その目的も違うことを理解することが重要です。
- 電気工事業登録:
- 根拠法: 電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)
- 目的: 電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資すること
- 対象:一般用電気工事及び自家用電気工事 を営む事業者が対象です。
- 建設業許可:
- 根拠法: 建設業法
- 目的: 建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与すること
- 対象: 一般的に500万円以上の請負金額の工事を営む事業者が対象です。
このように、法律も目的も全く異なるため、どちらか一方があればもう一方が不要になる、という関係性ではありません。
2:なぜ建設業許可があっても登録が必要なのか?
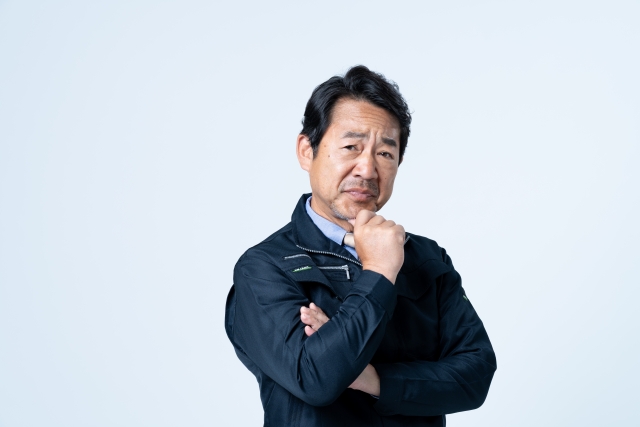
建設業許可を持っている事業者は、「みなし登録電気工事業者」として、電気工事業法上の登録が「不要」になる場合があります。しかし、これは「登録が免除される」わけではなく、別途、建設業許可を取得していることを都道府県知事に届け出る必要があります。
この届け出をしないまま電気工事業を営むと、無登録電気工事業者となり、罰則の対象となる可能性があります。
具体的な手続きの流れ:
- 建設業許可を取得する。
- 建設業許可取得後、遅滞なく、管轄の都道府県知事または経済産業大臣に電気工事業の開始届出書を提出する。
- この通知手続きを行うことで、初めて「みなし登録電気工事業者」として、電気工事業法上の登録が完了したことになります。
つまり、「建設業許可があれば登録は不要」という認識は、手続きが不要という意味ではなく、改めて登録申請書を提出する手間が省けるという表現が正しいのです。
3:電気工事業登録が「不要」な例外とは?
電気工事業登録が不要となるのは、以下のような工事を行う場合です。
- 電気工事に該当しない軽微な工事のみを扱う場合
- 軽微な工事に該当する例: 差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又はナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事、電気機器(配線器具を除く。以下同じ)の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をネジ止めする工事等
- 家庭用の家電製品の販売に伴い、サービスとして設置工事を行う場合
- 自社で作業はせず、元請としてほかの業者へ作業を発注する場合
4:建設業許可と電気工事業登録の取得条件比較
両方の制度を理解するために、それぞれの取得条件を比較してみましょう。
| 項目 | 建設業許可(電気工事業) | 電気工事業登録 |
| 対象工事 | 500万円以上の工事 | ほぼすべての電気工事 |
| 技術者 | 専任技術者を設置する必要がある | 主任電気工事士を設置する必要がある |
| 主な要件 | ・経営業務の管理責任者がいる ・専任技術者がいる ・財産的基礎(自己資本500万円以上など) ・欠格要件に該当しない | ・主任電気工事士がいる ・器具(絶縁抵抗計、接地抵抗計など)がある |
注目すべきポイント:
- 技術者要件: 建設業許可と電気工事業登録では、求められる技術者の役割が異なります。
- 建設業許可の専任技術者: 営業所に常勤し、工事全体の技術的側面を統括する責任者。
- 電気工事業登録の主任電気工事士: 電気工事士の中から選任され、工事の管理を行う責任者。
- 器具要件: 電気工事業登録では、安全な工事を行うために、法律で定められた試験器具(絶縁抵抗計など)を所有していることが求められます。建設業許可にはこの要件はありません。
5:まとめ:両方の取得が事業拡大の鍵

「建設業許可があれば電気工事業登録は不要?」という疑問に対する答えは、「必要」です。
電気工事業を営む事業者は、原則として電気工事業法に基づく登録が必須であり、これを行わずに営業することは違法となります。建設業許可は、あくまで「大規模な電気工事」を請け負うための資格であり、電気工事全体の安全性を担保する電気工事業法上の義務を免除するものではありません。
今後、事業を拡大し、元請けとして大きな工事も請け負いたい場合は、両方の制度を理解し、計画的に手続きを進めることが重要です。
- 軽微な電気工事のみを請け負う場合は、どちらも不要。
- 500万円未満の工事を請け負う場合は、電気工事業登録が必須。
- 500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必須。
- 建設業許可を取得している場合は、みなし登録のための届出が必須。
どちらの制度も、社会の安全と事業者の信用を守るためのものです。正しい知識を持って、適正な手続きを行うことが、長期的な事業成功への第一歩となります。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
建設業許可はもちろん、電気工事業登録も取扱っております。ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力で事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。



