【コンビニ開業】必要な資格や許可が知りたい!行政書士が徹底解説
【コンビニ開業】必要な資格や許可が知りたい!行政書士が徹底解説

「コンビニを経営したい!」と考えている方へ。コンビニ開業は、様々な商品を扱う特性上、法律で定められた多くの資格や許可が必要になります。
「何から手をつけていいか分からない」「手続きが複雑そう…」と感じる方も多いでしょう。
この記事では、コンビニ開業に必須となる資格・許可、そして複雑な手続きをスムーズに進めるための行政書士の活用法について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
これからコンビニ開業を考えている方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
090-9451-9906(担当:茂木)
1|コンビニ開業で「必須」となる主な資格

コンビニでは飲食物、酒類、たばこなど多岐にわたる商品を扱います。そのため、取り扱い商品や店舗規模に応じて、複数の資格が必要となります。
| 資格名 | 目的・必要性 | 取得方法 |
| 食品衛生責任者 | 食品の衛生管理を行う責任者。食品を取り扱うすべての店舗に1名以上の設置が義務付けられています。 飲食店営業許可を取得するために配置する必要があります。 | 各自治体の食品衛生協会が実施する講習会(1日)を受講。調理師免許などの資格があれば免除。 |
| 防火管理者 | 火災による被害を防ぐための責任者。収容人数が30人以上の店舗は選任が義務付けられています。 | 消防署などが実施する講習会を受講(甲種・乙種の区分あり)。コンビニの建物面積(多くは300㎡未満)に応じて乙種を取得するケースが多いです。 |
| 酒類販売管理者 | 酒類の販売業務に関するルールを遵守させるための責任者。酒類販売免許を取得する際に、販売場ごとに選任が必要です。 | 国税庁が指定した研修実施団体(フランチャイズ本部など)が実施する研修(3時間程度)を受講。 |
【補足】安全衛生推進者が必要になる場合も
従業員(アルバイト・パート含む)を常時10人以上50人未満使用するコンビニを開業する場合、安全衛生推進者の選任が必要です。これは、職場の安全衛生管理を推進するための役割を担います。
- 取得方法: 2日間にわたる講習の受講が必要です。
2|コンビニ開業で「必須」となる主な許可・届出
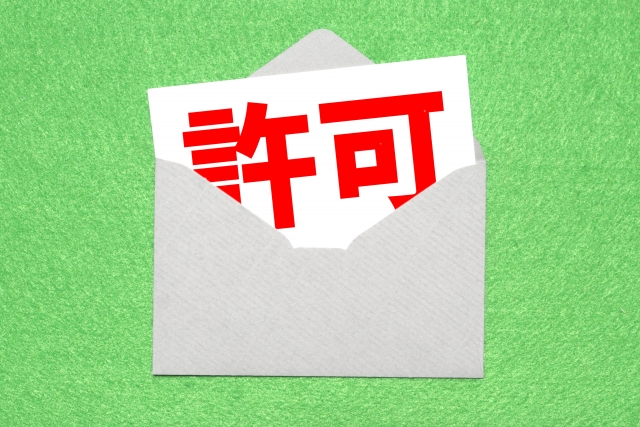
資格と並行して、商品の販売や店舗の営業自体に関わるさまざまな「許可」や「届出」が必要です。
| 許可・届出名 | 目的・必要性 | 申請先 |
| 飲食店営業許可 | 店内で調理・加工するファストフード(おでん、フランクフルトなど)を販売する場合に必要です。 | 保健所 |
| 食品販売業の許可 | 生鮮食品(乳類、食肉、魚介類など)を取り扱う場合に、品目に応じて個別の許可が必要です。 | 保健所 |
| 一般酒類小売業免許 | 店頭で酒類を販売するために必須の免許です。販売場ごとに取得が必要です。 | 税務署 |
| 製造たばこ小売販売業許可 | たばこを販売するために必須の許可です。店舗間の距離基準など、厳しい要件がある点に注意が必要です。 | 財務省(所管のJT営業所経由など) |
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 事業を開始したことを税務署に届け出るための書類です。(法人の場合は法人設立届出書) | 税務署 |
| 防火管理者選任届 | 防火管理者を選任した際に届け出る必要があります。 | 消防署 |
許可取得の重要ポイント:内装工事の前に「事前相談」を!
食品に関する営業許可(飲食店営業許可、食品販売業許可)を取得するには、店舗の設備や構造が保健所の定める基準を満たしている必要があります。
内装工事が完了した後で基準を満たしていないことが判明すると、手直しが必要になり、追加コストや開業の遅れにつながる可能性があります。
そのため、店舗設計の段階で必ず保健所に事前相談を行い、必要な設備(シンクの数、手洗い設備、床や壁の材質など)を確認することが極めて重要です。
090-9451-9906(担当:茂木)
3|許可取得までの流れと期間の目安

必要な資格や許可によって手続きの順番は前後しますが、主な流れは以下のようになります。
- 物件の選定・内装工事の着工
- (同時並行)各種資格の取得
- 食品衛生責任者講習(1日)
- 防火管理者講習(1〜2日)など
- 内装工事完成前(目安10日~2週間前):各種許可の申請
- 飲食店営業許可申請(保健所)
- 一般酒類小売業免許申請(税務署)など
- 内装工事完成後:保健所・消防署による施設検査
- 審査を経て、各種許可証の交付
- 開業(税務署への開業届提出など)
すべての手続きをスムーズに進めたとしても、特に時間のかかる酒類販売免許の審査や、保健所の検査日程の調整などを考慮すると、開業まで数ヶ月を要するのが一般的です。
4|資格・許可の手続きは行政書士に依頼すべき?

「開業準備で忙しいのに、複雑な申請手続きに時間を割きたくない」「手続きに不備があって開業が遅れるのは避けたい」
このように感じる方にとって、行政書士への依頼は非常に有効な手段となります。
行政書士に依頼するメリット
- 手続きのプロによる確実なサポート
- 行政書士は、官公署に提出する書類作成のプロです。申請書類の不備による再提出や開業の遅れを防げます。
- 煩雑な作業から解放される
- 行政書士が申請書類の作成、収集、提出、各役所(保健所、税務署、消防署など)との事前調整や折衝を代行するため、オーナーは店舗運営や集客などの準備に集中できます。
- 内装段階でのアドバイス
- 営業許可に詳しい行政書士であれば、物件や内装設計の初期段階で「この設備だと許可が下りない可能性がある」といった専門的な視点からの助言を得られ、手戻りを防止できます。
依頼する際の費用相場
行政書士に依頼する場合、依頼内容によって費用は異なりますが、主な許可の報酬相場は以下のようになります。
| 依頼する手続き | 行政書士報酬の目安 |
| 飲食店営業許可申請 | 4万円〜6万円程度 |
| 一般酒類小売業免許申請 | 12万円〜15万円程度 |
※上記に加え、申請手数料が別途かかります。実際の費用は、行政書士事務所や地域、店舗の状況によって異なります。
申請手数料は実費としている事務所が多く見受けられます。
090-9451-9906(担当:茂木)
5|まとめ:計画的な準備と専門家の活用で確実な開業を

コンビニ開業には、「食品衛生責任者」「防火管理者」といった資格や、「飲食店営業許可」「一般酒類小売業免許」といった多岐にわたる許可が必要です。
特に、内装工事に取り掛かる前の保健所への事前相談や、酒類販売免許の審査期間を考慮した計画的な準備が成功の鍵となります。
手続きの複雑さや、万が一の不備による開業の遅れを避けたい方は、許可申請のプロである行政書士に相談することを強くおすすめします。
専門家のサポートを上手に活用し、安心してコンビニ開業をスタートさせましょう。
弊所のご紹介
弊所は各種許認可に特化した行政書士事務所です。
飲食店許可はもちろん、酒類販売免許やたばこ販売業許可も取扱っております。ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。




