【法人成り】建設業許可を承継する手続きの流れを行政書士が徹底解説!
【法人成り】建設業許可を承継する手続きの流れを行政書士が徹底解説
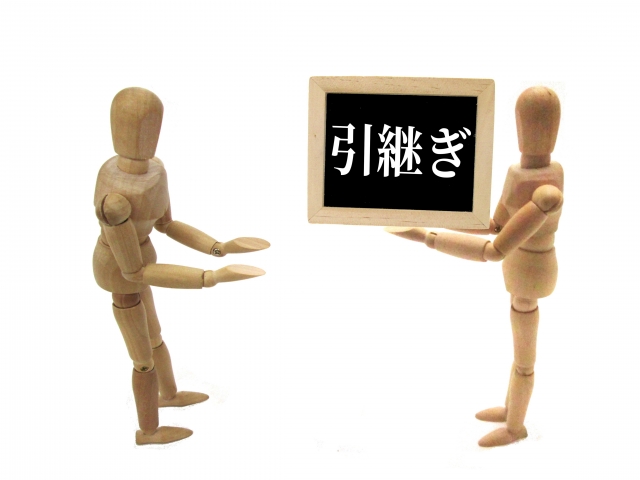
個人事業主として建設業を営む方々にとって、事業拡大や税制優遇を目的とした「法人成り」は、さらなる飛躍のための重要な決断です。
それと同時に問題となってくるのが、建設業許可です。
従来、個人名義の建設業許可は法人へは引き継げず、「廃業+新規申請」で許可を取り直す必要がありました。このため、一時的に無許可状態が発生するリスクや、許可番号が変わってしまう問題がありました。
しかし、令和2年施行の改正建設業法により、この状況は大きく変わりました。新たに導入された「事業承継の事前認可制度」を利用することで、個人事業主が新設する法人へ、建設業許可の「地位の全部」を空白期間なく承継することが可能になったのです。
この記事では、この制度を利用した個人事業主の「事業譲渡による法人成り」に焦点を当て、その具体的な手続きの流れ、要件、そして注意点を最新情報で行政書士が徹底解説します。
目次
1|令和2年改正で新設された「地位の承継」制度とは

法人成りで建設業許可を引き継ぐ際、知っておくべき改正法のポイントを解説します。
1. 「事業譲渡」による地位承継が可能に
改正法により、建設業許可の承継は以下の4パターンで可能になりましたが、個人事業主の法人成りでは主に「事業の譲渡及び譲受け」の規定を利用します。
- 譲渡及び譲受け(個人事業主から新設法人への事業譲渡など)
- 合併
- 会社分割
- 相続(個人事業主の死亡時)
この制度を利用し、行政庁の「事前認可」を受けることで、新設法人は個人事業主の建設業者としての地位(許可番号、有効期間、経営事項審査の結果など)を、そのまま引き継ぐことができます。
2. 最大のメリットは「空白期間の回避」と「許可番号の維持」
- 空白期間の回避: 事前認可を受けることで、事業譲渡の効力発生日をもって許可が承継されるため、無許可期間が一切発生しません。
- 許可番号の維持: 新規申請とは異なり、個人事業主が持っていた許可番号が新法人にそのまま引き継がれるため、取引先への変更手続きも簡略化されます。
3. 「新規申請」から「事前認可申請」へ
従来の新規申請と異なり、承継手続きは「事前認可申請」という形になります。審査に通ると、許可の有効期間も承継の効力発生日の翌日から改めて5年間となります。
2|法人成りによる許可承継の具体的な手続きの流れ

事業承継による法人成りで、建設業許可を円滑に引き継ぐための具体的なステップと時系列を解説します。
手続きの流れ(時系列順)
(1) 新設法人の設立(登記完了)
個人事業主が事業を譲り渡す相手として、先に新設法人を設立・登記します。この法人が、承継後の建設業者となります。
(2) 事前相談・準備(効力発生日の約4ヶ月前)
認可申請を行う前に、必ず管轄の行政庁(都道府県庁等)に事前相談を行います。この際、事業譲渡の概要や、承継後の法人が許可要件を満たす見込みがあることを伝えます。
(3) 事業譲渡契約の締結と株主総会の決議
個人事業主と新設法人との間で、建設業に関する事業の全部を譲渡・譲受する旨の「事業譲渡契約書」を締結します。
(4) 建設業許可「地位の承継認可申請」(効力発生日の約2ヶ月前)
事業譲渡契約や新設法人の許可要件に関する書類を揃え、「承継認可申請書」を提出します。認可申請は事業譲渡の効力発生日30日前までに行う必要があります。
(5) 審査と認可(効力発生日の直前)
行政庁による審査が行われます。審査期間は都道府県により異なりますが、概ね1か月~2か月程度が目安です。審査が完了すると、認可書が交付されます。
(6) 承継の効力発生と届出
認可書に記載された効力発生日をもって、新設法人は個人事業主の建設業者としての地位を正式に承継します。効力発生後、遅滞なく個人事業主(旧業者)の廃業届を提出します。
3|地位の承継認可に必要な要件と注意点

事前認可を得るためには、新設法人が許可要件を満たしていることに加え、いくつかの承継特有の要件があります。
1. 承継の範囲:「全部承継」が原則
- 建設業の全部承継: 個人事業主が有していた建設業許可業種の全部を新設法人が承継しなければなりません。例えば、個人が「土木工事業」と「とび・土工工事業」の2つを持っていた場合、両方とも承継する必要があります。
- 一部のみを承継しない場合: もし一部の業種を承継したくない場合は、認可申請を行う前に個人事業主がその業種の廃業届を提出しておく必要があります。
2. 承継後の許可要件の確認(経管・専技・財産的基礎)
新設法人は、承継後に有することとなる全ての許可業種について、建設業許可要件を具備している必要があります。
| 要件 | 確認ポイント |
| 経営業務の管理責任者 | 譲渡人(個人事業主)が、譲受人(新設法人)の常勤役員等となり、個人事業主時代の経験を引き継いで経管の要件を満たすこと。 別記事:難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策 |
| 営業所技術者(旧専任技術者) | 個人事業の専任技術者であった者が、承継後も引き続き新設法人で常勤し、専任技術者として配置されること。 別記事:資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説! |
| 財産的基礎 | 新設法人の資本金や残高証明により、一般建設業であれば500万円以上の財産的基礎を有すること。 |
| 社会保険 | 法人設立に伴い、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適正に加入していること。 別記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説! |
3. 制度特有の注意点
- 罰則の不承継: 承継前の個人事業主が受けた行政処分(指示処分や営業停止処分)は承継されますが、建設業法上の罰則(罰金など)は承継されません。
- 決算変更届の義務: 承継後の新設法人は、被承継者(個人事業主)の未提出の決算変更届(事業年度終了届)がある場合、それを代わって作成・提出する義務を負います。
- 承継日以前の変更届: 認可申請時点で、個人事業主または新設法人の届出事項に変更がある場合は、認可申請の前に変更届を提出しておく必要があります。
4|スムーズな移行のためのタイムスケジュールと行政書士の活用

計画的な手続きが成功の鍵
事前認可制度は、従来の新規申請よりも手続きが複雑であり、行政庁との事前相談と綿密な調整が不可欠です。特に、効力発生日の2ヶ月前までに事前相談を行うことが推奨されており、計画性のない申請は審査が長期化する原因となります。
| フェーズ | 目安期間 | 重要なアクション |
| I. 準備 | 効力発生日の6ヶ月前 | 行政書士への相談、法人設立登記、事業譲渡契約案の作成。 |
| II. 相談 | 効力発生日の4ヶ月前 | 管轄行政庁へ事前相談、必要書類の確認・収集。 |
| III. 申請 | 効力発生日の2ヶ月前 | 承継認可申請書提出。 |
| IV. 完了 | 効力発生日当日 | 認可が有効化、個人事業主の廃業届提出。 |
行政書士に依頼する最大のメリット
- 制度への精通: 令和2年改正で新設された制度は、通常の新規申請とは異なる専門知識と運用ノウハウが必要です。行政書士は、最新のガイドラインに基づき、確実な承継をサポートします。
- 書類作成の正確性: 煩雑な事業譲渡契約書や、株主総会議事録など、法的な効力が求められる書類作成を適切に行います。
- 行政との折衝: 事前相談の段階から行政庁との調整を代行し、審査期間の長期化を防ぎます。
5|新制度を活かし、空白期間のない事業継続を実現しよう

令和2年改正建設業法によって、個人事業主の事業者は「法人成り」の際、許可の空白期間や許可番号の変更といったリスクを気にすることなく、事業を継続できるようになりました。
この地位の承継認可制度は、個人事業主としての実績と信用を新設法人へ完全に引き継ぐための強力なツールです。複雑な要件や手続きをクリアし、適法かつ円滑な移行を実現するため、建設業許可に精通した行政書士にご相談ください。弊所も、建設業許可をメインに取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。



