【建設業許可の要件】営業所として認められる要件とは。自宅でもOK?行政書士が徹底解説!
【建設業許可の要件】営業所として認められる要件とは。自宅でもOK?行政書士が徹底解説!

建設業で一定規模以上の工事を請け負う場合、「建設業許可」の取得が法律で義務付けられています。この許可を取得する上で、避けて通れないのが「営業所」に関する要件です。
建設業の営業所は、単に工事の「契約書」や「請求書」のやり取りをする場所というだけでなく、建設工事の請負契約を締結し、かつ、継続的に業務を行う場所として、許可要件の中心的な役割を担います。
「これから独立して許可を取りたいけど、立派な事務所を借りる余裕はない…」「自宅を営業所にできるのかな?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、建設業に特化したの行政書士が、建設業許可における営業所の定義、満たすべき要件、そして「自宅兼事務所」の可否について、詳しく解説します。
これから建設業許可を取得しようとお考えの方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
1|建設業許可における「営業所」の定義と役割

建設業許可における「営業所」とは、単なる事務スペースではありません。国土交通省の指導基準に基づき、以下の役割を担う場所と定義されています。
1. 営業所の主な役割
- 請負契約の締結を行う場所:元請け・下請けに関わらず、建設工事の請負契約を実質的に締結する機能を持ちます。
- 継続的に業務を行う場所:単発的な利用ではなく、経営業務や技術的な業務を継続的に行っている必要があります。
- 重要な人物が常駐する場所:許可の人的要件である「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」および「営業所技術者技術者等(旧専任技術者)」が常時勤務する場所でなければなりません。
2. 営業所の設置が求められる理由
そもそも、なぜこのように厳格な「営業所」の要件が求められるのでしょうか。
それは、建設業の取引の適正化と発注者の保護のためです。しっかりとした拠点がなければ、契約や施工に問題が生じた際、責任の所在が不明確になったり、事業者が逃げてしまったりするリスクが高まります。
営業所が存在し、そこに重要な責任者が常駐することで、その事業者が「まっとうな事業活動を継続的に行う体制が整っている」と行政が判断する根拠となるのです。
2|自宅は営業所として認められる?要件を徹底解説!
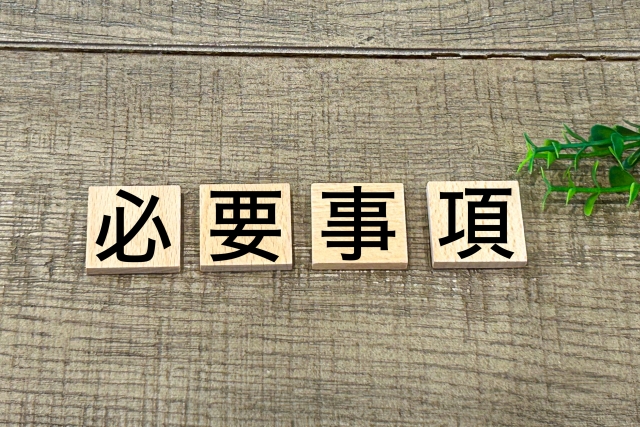
「自宅を営業所にしたい」という相談は非常に多いですが、結論から言えば、要件さえ満たせば「自宅兼事務所」は建設業許可の営業所として認められます。
ただし、「自宅と事務所を一緒にしたいから」という理由だけで認められるわけではありません。自宅を営業所とする場合にクリアすべき、具体的な要件を見ていきましょう。
1. 必須要件:独立性と実態性
自宅を営業所として認めてもらうために最も重要となるのが、その場所が「独立性」と「実態性」を持っていることです。
物理的な「独立性」
営業所として使用する部分が、生活スペース(居住部分)とはっきり区別されている必要があります。
- 理想的な例:建物の入り口が住居と事務所で分かれている、または内部で壁や間仕切りによって完全に区切られ、鍵がかけられるようになっている。
- 最低限必要な措置:居住部分とは明確に区分された専用の部屋があり、その部屋が専ら事務作業に使用されていること。ふすまやカーテンでの仕切りでは不十分とされるケースがあります。
物理的に区切られていない場合、「事業に必要なプライバシーや機密性が確保できない」と判断され、営業所として認められない可能性が高くなります。
機能的な「実態性」
その場所が単なる「自宅」ではなく、「営業所」として機能していることが確認できなければなりません。
- 看板等の設置:社名や屋号、営業所名を表示した看板や表札が外部から容易に確認できる場所に設置されていること。(マンションやアパートの場合は、共用部分に設置できない場合、ポストや玄関に貼り紙をするなど代替措置が認められるケースもありますが、事前に許可行政庁に相談しましょう。)
- 設備:業務に必要な机、イス、PC、電話などの事務機器が設置されていること。
- 来客対応:来客対応や面談が可能なスペースがあること。
これらの実態が、申請時の写真添付によって厳しくチェックされます。
2. 不動産の使用権原の要件
自宅が自己所有か賃貸かで、提出書類が変わります。
自己所有の場合
- 登記事項証明書
- 固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書
のいずれか、または両方求められる場合もあります。個人事業主での申請の場合は住民票も求められる可能性があります。
賃貸物件の場合
- 賃貸借契約書(写し)
- 重要な注意点:契約書の「用途」欄が「住居専用」となっている場合、原則として営業所としては認められません。
- 対策:必ず貸主(大家さんや管理会社)に相談し、「事務所利用の承諾」を得て、書面(使用承諾書)を提出する必要があります。この承諾が得られない場合は、その賃貸物件を営業所とすることは非常に困難です。
3. ビル・テナントを借りる場合と自宅の比較
| 項目 | テナントビル等の場合 | 自宅兼事務所の場合 |
| 独立性 | 原則として問題なし | 生活スペースと完全に区切る必要あり |
| 実態性 | 看板設置、事務機器の設置は容易 | 看板設置場所、来客対応スペースに注意 |
| 費用 | 家賃・光熱費が事業経費として計上しやすい | 家賃・光熱費の按分計算が必要 |
| 使用権原 | 契約書の「用途」が「事務所」ならOK | 賃貸の場合、大家の承諾が必須 |
| 利便性 | 顧客からのアクセス、立地条件が良い | 通勤時間がかからない |
テナントを借りる方が手続き上はスムーズですが、費用面で負担が大きくなります。自宅を営業所とする場合は、行政庁が納得するだけの「物理的な独立性」を確保するための準備と、賃貸物件の場合は「大家の承諾」が最大のカギとなります。
3|営業所の審査で失敗しないための行政書士からのアドバイス

建設業許可の申請において、営業所に関する要件のチェックは非常に厳格に行われます。申請がスムーズに進むよう、以下のポイントを参考に準備を進めてください。
1. 営業所技術者・経営管理責任者の「常勤性」を確保
営業所として認められるためには、そこで働くべき「営業所技術者」や「常勤役員等」がその営業所に常時勤務(常勤)していることが必須です。
別記事:・難解な要件をクリア!経営業務の管理責任者証明のポイントとケース別対応策
・資格と実務経験が鍵! 建設業許可の営業所技術者(専任技術者)の要件を分かりやすく解説!
自宅兼事務所の場合、この常勤性がより厳しくチェックされることがあります。
- 常勤性の証明:申請書類に記載する勤務地は当然その営業所とし、必要に応じて通勤手段や時間なども確認されます。
2. 賃貸契約場合「用途」は必ず確認を
先述の通り、賃貸物件の場合「住居専用」の契約のまま無断で事務所として利用することは絶対に避けてください。
- 大家さんや管理会社に正直に事情を説明し、建設業許可の営業所として使用したい旨を伝える。
- 契約書の「用途」を「事務所(または住居兼事務所)」に変更してもらうか、別途「事務所使用承諾書」を作成してもらう。
この準備を怠ると、申請段階で許可が下りないだけでなく、後々の契約違反にもつながりかねません。
3. 契約書等の保管場所を明確に
営業所の「実態性」を示すために、建設業の業務に関する書類(契約書、見積書、図面、帳簿類など)が、その営業所に適切に保管されていることが求められます。
申請の際には、これらの書類を保管する棚やロッカーの写真を求められることもあります。単なる物置ではなく、事業の中枢として機能していることを写真で証明できるようにしましょう。
4. 事前相談の徹底
営業所の独立性の判断は、行政庁(都道府県庁の担当課など)によって若干のローカルルールや解釈の違いがある場合があります。
「自宅の一室を営業所にしたいが、この間取りで大丈夫か」「看板は玄関先に置くことで認めてもらえるか」など、疑問点や懸念点がある場合は、申請前に必ず行政書士を通じて行政庁に事前相談を行うことを強く推奨します。
「許可申請自体は自分でやる」という場合でも、事前相談をすることにより許可取得までスムーズに進めることが出来ます。
4|まとめ:成功への第一歩は「適正な営業所」から
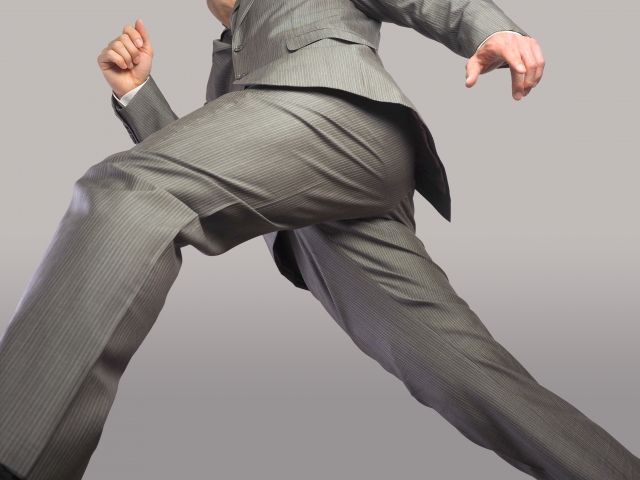
建設業許可の取得は、事業の信用を高め、請負える工事の幅を広げるための重要なステップです。許可取得への第一歩として、「適正な営業所」の準備を早速始めましょう。
特に自宅を営業所とする場合は
- 物理的な独立性(生活スペースとの明確な区別)
- 機能的な実態性(看板、事務機器、書類の保管)
- 賃貸の場合は貸主の明確な承諾
の3点を徹底的にクリアすることが成功のカギとなります。
建設業許可申請は、準備すべき書類が多く、法令の解釈も複雑です。専門的な知識と経験を持つ行政書士に依頼することで、営業所に関する要件のチェックはもちろん、経営管理体制や専任技術者の要件など、その他の複雑な手続きもスムーズに進めることが可能となります。
「自宅で許可を取りたい」「営業所の要件が不安だ」という方は、是非一度、建設業許可に特化した行政書士にご相談しましょう。弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所ですので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
建設業許可を取得して、さらなる事業拡大を目指していきましょう。



