「居酒屋開業」に必要な資格や許可を徹底解説!【行政書士監修】
「居酒屋開業」に必要な資格や許可を徹底解説!【行政書士監修】

「居酒屋を開業したい!」美味しい料理やお酒、素敵な空間を提供したいという情熱は大切ですが、その夢を実現するためには、避けて通れないのが「資格」や「許可」の取得です。
「資格と許可、何が違うの?」と戸惑う方も多いでしょう。法律上は、資格は特定の行為を行う能力を公的に証明するもの(例:調理師免許)、許可は行政機関が特定の行為をすることを認める行為(例:飲食店営業許可)を指しますが、開業準備においては、「行政に申請して取得する必要があるもの」と捉えていただいて大丈夫です。
この記事では、行政書士が、一般的な居酒屋はもちろん、多様なスタイルの居酒屋で必要となる「行政への申請(許可・届出)」や「必ず設置・取得が必要な資格」をパターン別に分かりやすく解説します。これから居酒屋の開業をお考えの方は、自分はどのパターンに当てはまるのかを考えながら、ご参考にしてください。
目次
1|全ての居酒屋に共通して必要な「基本の許可・資格」

居酒屋の形態に関わらず、飲食物を提供し、お客様から代金を受け取る事業を行う上で、必ず必要となるのが以下の2つです。
1. 必須の「行政の許可・届出」
| 必要な許可・届出 | 管轄行政機関 | 概要 | 備考 |
| 飲食店営業許可 | 保健所 | 飲食物を提供する全ての飲食店に必須の許可。 | 内装や設備が基準を満たしているかチェックされます。 食品衛生責任者の配置も必要です。 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 警察署 | 深夜(午前0時~午前6時)にお酒を提供する居酒屋は必須。 | 届出をしないと無許可営業となります。 |
【深夜酒類提供飲食店営業開始届出書について補足】
- 「このような居酒屋であればこれはいらない」パターン:
- 午前0時までに閉店する居酒屋や、深夜に提供する主たるものが食事(ラーメン店など)で、お酒が主ではないと認められる場合は、この届出は不要です。
- この届出には、店舗の場所や構造(客室の床面積など)に関する厳格な基準があります。特に、住居専用地域では原則として営業できませんので、物件選びの段階で確認が必要です。
別記事:深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?対象・必要書類・申請先を徹底解説!
2. 必須の「資格(責任者の設置)」
| 必要な資格・責任者 | 管轄行政機関/団体 | 概要 | 備考 |
| 食品衛生責任者 | 保健所 | 各店舗に必ず1名設置が義務付けられています。 | 講習会を受講するか、調理師などの資格があればなれます。飲食店営業許可を取得する際に配置が必須です。 |
| 防火管理者 | 消防署 | お客様の収容人数が30人以上の店舗は、必ず選任が必要。 | 収容人数に応じて「甲種」または「乙種」の講習を受講します。 |
別記事:食品衛生責任者の資格は講習で取れる!知っておきたい取得方法と費用
【防火管理者について補足】
- 「このような居酒屋であればこれはいらない」パターン:
- お客様と従業員を合わせた店舗全体の収容人数が30人未満の小規模な居酒屋やバーは、原則として選任・届出は不要です。
- ただし、この人数にはオーナーやアルバイトなどの従業員も含まれるため、余裕を持って確認が必要です。
- 賃貸ビルなどで、ビル全体の防火管理者がいる場合でも、店舗ごとに選任が必要となるケースが一般的です。
2|居酒屋のスタイル・提供方法によって必要になる「特別な許可」
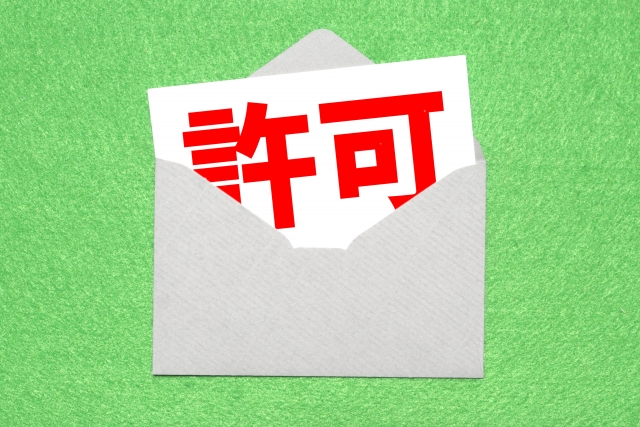
一般的な居酒屋のスタイルから外れたり、特殊なサービスを提供する場合は、上記に加えて以下の許可が必要になる可能性があります。
1. 【お酒の提供方法】に関する許可
| 居酒屋のスタイル | 必要な許可・届出 | 管轄行政機関 | 概要 |
| テイクアウトやデリバリーでお酒を販売する | 酒類小売業免許 | 税務署 | 店頭で瓶ビールなどを持ち帰り用に売ったり、デリバリーで未開封のお酒を売る場合に必要。 |
| 「立ち飲み」スタイルをメインにする | 特に新たな許可は不要 | - | 飲食店営業許可の範囲内。 |
| 店内で調理した料理をテイクアウト・デリバリーする | 特に新たな許可は不要 | - | 飲食店営業許可の範囲内。ただし、食品の種類(菓子、アイス等)によっては新たに許可が必要。 |
【酒類小売業免許について補足】
- 「このような居酒屋であればこれはいらない」パターン:
- 店内でグラスなどに注いで提供するだけで、未開封の酒類(缶、瓶など)を持ち帰り用に販売しない居酒屋は不要です。
2. 【エンターテイメント・接待】に関する許可
居酒屋でお客様を楽しませる方法によって、規制の対象となることがあります。
| 居酒屋のスタイル | 必要な許可・届出 | 管轄行政機関 | 概要 |
| ホステスによる接待(隣に座って談笑、カラオケのデュエットなど)を行う居酒屋 | 風俗営業許可 | 警察署 | いわゆる「スナック」「キャバクラ」の形態に該当する場合は必須。 |
| 生演奏、ダンス、ショーなどの興行を行う居酒屋(例:ライブ居酒屋) | 特定遊興飲食店営業許可 | 警察署など | 規模や内容によっては、風俗営業法の規制対象となる場合があるため、事前相談が必須。 |
| ダーツ、カラオケをお客様自身で楽しんでもらう | 特に新たな許可は不要 | - | 「接待」と見なされない範囲であれば、飲食店営業許可の範囲内。 |
【風俗営業許可について補足】
- 「このような居酒屋であればこれはいらない」パターン:
- お客様の隣に座ってサービスを提供しない、料理やお酒の提供のみを行う一般的な居酒屋は不要です。
- 従業員がカウンター越しにお酒を提供するだけのバーも、基本的にこの許可は不要です。(ただし、過度な身振り手振りや会話が「接待」と見なされないように注意が必要です。)
- 風俗営業許可は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書よりもさらに立地条件が厳しく、取得が非常に困難な地域が多いです。
3. 【提供する飲食物】に関する許可
| 居酒屋のスタイル | 必要な許可・届出 | 管轄行政機関 | 概要 |
| 自家醸造のビールやどぶろくを提供する | 酒類製造免許 | 税務署 | 自分で醸造したお酒を提供する場合に必要。取得のハードルは極めて高い。 |
| 食肉(生肉)を生食用として提供する | 生食用食肉取扱の届出 | 保健所 | ユッケ、レバ刺し(加熱用でないもの)などを提供する際に必要。 |
| ふぐ料理を提供する居酒屋 | ふぐ調理師免許とふぐ提供施設届出 | 都道府県 | 専門的な資格と届出が必須。 |
3|開業前に済ませておくべき「その他の届出」

許可や資格ではありませんが、事業を始める上で必ず必要となる行政への届出です。
| 必要な届出 | 管轄行政機関 | 概要 | 備考 |
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 税務署 | 居酒屋を事業として始めることの届出。 | 開業から1ヶ月以内。 |
| 青色申告承認申請書 | 税務署 | 節税効果の高い「青色申告」をする場合に必要。 | 開業から2ヶ月以内。 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 税務署 | 従業員を1人でも雇う場合に必要。 | |
| 労働保険の保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 従業員を雇用する場合に必須の保険手続き。 | |
| 社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用届 | 年金事務所 | 従業員数や法人の場合に加入義務が発生。 |
4|居酒屋開業の「許可・資格」取得フロー(大まかな流れ)

多くの居酒屋オーナーが辿る基本的な流れは以下の通りです。
- 物件の選定:まずは物件が「飲食店営業許可」や「深夜酒類提供の届出」の立地条件を満たしているか行政書士などに確認。
- 食品衛生責任者の確保:食品衛生責任者となる者を決めます。
- 内装・設備の工事:保健所の基準を満たすよう、図面段階から保健所に相談しながら進めます。
- 飲食店営業許可の申請:工事完了予定の2週間ほど前に保健所に申請。
- 保健所の立ち会い検査:設備が基準通りかチェックを受けます。
- 許可証の交付:問題なければ許可証が交付されます。
- 深夜営業の届出:午前0時以降も営業する場合は、警察署へ届け出ます。
- 防火管理者の選任・届出:収容人数30人以上の場合は、消防署へ届け出ます。
- 開業届:税務署に提出し、事業をスタートします。
5|まとめ:許可なくして居酒屋なし!

居酒屋を開業するには、「飲食店営業許可」「食品衛生責任者」が最低限の必須事項となります。
さらに、深夜営業を行うなら「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」、収容人数が多いなら「防火管理者」、特殊なサービス(接待など)をするなら「風俗営業許可」といった追加の許可が必要となります。
特に「深夜営業」と「接待(風俗営業)」は、物件の立地条件が厳しく定められているため、物件を契約する前に、行政書士などの専門家に相談することが、失敗しない居酒屋開業の鍵となります。事前に準備をしっかりとして、スムーズな開業を目指しましょう。



