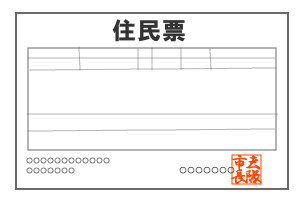建設業者は産業廃棄物処理業の許可が必要か?「建設業許可」と「廃棄物処理法」の適用関係を徹底解説
建設業者は産業廃棄物処理業の許可が必要か?「建設業許可」と「廃棄物処理法」の適用関係を徹底解説

建設業を営む皆さまにとって、「建設業許可」の取得・維持はビジネスの根幹です。しかし、建設業許可はあくまでも「工事」に関する許可です。請け負った工事で必ず発生する「産業廃棄物(産廃)」の取り扱いには、建設業法とは全く別の法律である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、略して廃掃法)」が適用されます。
「工事はうちがやったんだから、自分たちで運んで捨ててしまおう」これは非常に危険な考え方です。多くの建設業者が「自社の事業で出たゴミだから」と安易に考えてしまいがちですが、この行為が無許可営業とみなされ、罰則(5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方)の対象となるケースが少なくありません。
この記事では、「自分の事業には産廃許可が必要なのか?」という疑問に対し、建設業許可を持つ事業者が産業廃棄物(特に建設廃棄物)を適法に取り扱うために知っておくべき、廃棄物処理法の基本原則と、建設業特有の「例外規定(自家処理の原則)」について、専門家である行政書士が分かりやすく解説します。少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
1|建設廃棄物の基礎知識:建設業特有の「産業廃棄物」とは

まず、建設工事で発生する廃棄物は、そのほとんどが廃棄物処理法上の「産業廃棄物」に該当します。
建設工事で発生する20種類の産廃
廃棄物処理法で定められる産業廃棄物は20種類ありますが、建設工事から排出されるものは特に「建設廃棄物」と呼ばれ、以下の種類が該当します。
- 廃プラスチック類 (ビニール、断熱材など)
- 木くず (型枠材、木材片など)
- 金属くず (鉄筋、足場材など)
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類 (特に解体工事で発生するコンクリート塊、アスファルト塊など)
- 紙くず、繊維くず (特定の事業活動に伴うもの)
- 廃油ゴムくず
- 汚泥
このうち、がれき類は、建築物等の建設、解体等に伴って生じたものに限り産業廃棄物として定義されています。
したがって、例えば「PCを向上で製造する際に出たコンクリート片」こちらは建設、解体時に発生したものではないため、がれき類ではなく、コンクリートくずに分類されます。見落としがちなポイントなので、注意しましょう。
違反リスクの高い行為:「処理」の厳格な定義
建設業者が最も注意すべきは、廃棄物処理法における「処理」の定義です。「処理」と聞くと、最終的に埋立したりする工程を思い浮かべるかと思います。しかし「処理」には、単に最終処分するだけでなく、中間処理(破砕、選別など)や「運搬」も含まれます。
すなわち、ダンプで建設現場から次の現場や処分場へ廃棄物を運ぶ行為も、原則として「産業廃棄物収集運搬業」に該当し、許可が必要となります。
だだし、完全に自社間で運搬を行う場合許可は不要です。(自社の現場で出た自社の廃棄物を自社まで運ぶ等)
2|産業廃棄物処理業の許可が必要な2つのケース

建設業者が廃棄物処理業の許可を必要とするのは、主に以下の2つのパターンです。
ケース①:他人の産業廃棄物を「収集運搬」または「処分」する場合
最も一般的なケースです。
- 行為: 他社(元請け、下請け、別の排出事業者など)が排出したがれき類や木くずを引き取り、運搬、または処分すること。
- 必要な許可:
- 運搬を行う場合:産業廃棄物収集運搬業許可
- 中間処理(破砕、焼却など)や最終処分を行う場合:産業廃棄物処分業許可
- 適用範囲: 運搬・処分を行う場所(都道府県)ごとに許可が必要です。
ケース②:自社の産業廃棄物であっても「他社の排出物」を運ぶ場合
建設業界特有の構造で発生しやすいのがこのケースです。
- 状況: 元請業者であるA社が、下請業者であるB社が排出した産業廃棄物(例えばB社の型枠解体後の木くず)を自社の車両で運搬する場合。
- 法的判断: A社にとっては、B社が排出した廃棄物は「他人の廃棄物」にあたるため、A社は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
なぜ元請け業者も許可が必要か?
建設業法では、元請業者が下請業者の廃棄物処理を指導・監督する責任(適正処理の確保)がありますが、運搬行為そのものには廃棄物処理法が適用されます。排出者が下請業者である以上、元請業者は「他人の産廃」を運ぶことになり、収集運搬業の許可が必要となるのです。
3|【最重要】建設業者が「産廃許可不要」となる唯一の例外規定

それでは、建設業許可を持つ企業が、一切の産廃許可なしで自社の車両を使って廃棄物を運搬できる例外規定はあるのでしょうか。
はい、あります。それが「排出事業者の自ら処理(自家処理)の原則」です。
許可が不要となる条件:「専ら自己の排出する産廃」の運搬
廃棄物処理法第14条には、「専ら自己の産業廃棄物を運搬する場合には、許可を必要としない」という例外規定があります。
建設業許可を持つ事業者が、この規定に基づいて許可が不要となるのは、以下のすべての条件を満たす場合です。
- 排出事業者であること: 運搬しようとする廃棄物が、運搬する自社の建設活動に伴って排出されたものであること。
- 自己の運搬であること: 運搬を自社の車両と自社の従業員のみで行うこと。
- 排出者責任を全うすること: 運搬の途中や、処分が完了するまで、適正な処理責任(飛散・流出防止、マニフェスト管理など)を負うこと。
具体的な適用例
- 許可不要のケース: 総合工事業のA社が、自社で施工した基礎工事から出た自社の残土(がれき類)を、A社のダンプとA社の社員で、A社の資材置き場に運搬する場合。
許可が必要となる(例外規定が適用されない)主なケース
自社の排出物であっても、以下のような行為には許可が必要です。
- 他社の車両・人を使う場合: 運搬の一部でも外部の運送業者に委託した場合。
- 下請けの廃棄物を運ぶ場合: 前述の通り、下請けが排出者は「他人の廃棄物」となる。
4|建設業許可と産廃処理許可の「経営業務管理体制」の違い
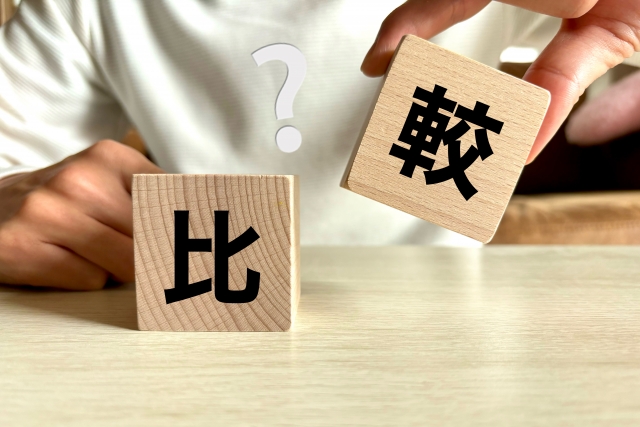
建設業許可(特に一般建設業)を取得している企業は、すでに「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を満たしています。しかし、産廃処理業の許可は「建設業許可」とは全く異なる独自の要件が求められます。
産廃処理業の許可要件(特に収集運搬業)
収集運搬業許可を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
| 要件項目 | 建設業許可(一般) | 産業廃棄物収集運搬業許可 | ニッチな違い |
| 経営能力 | 常勤役員等(旧:経管)の経験 | 廃棄物処理業に関する経理的基礎(債務超過でないこと)と知識・技術(講習会の修了) | 講習会の修了が必須であり、経営者に特定の知識が求められる。 |
| 技術能力 | 営業所技術者(旧:専技)の資格/実務経験 | 車両・運搬容器の適格性、積替え・保管施設の設置基準(積替えを行う場合) | 建設技術ではなく、廃棄物処理に関する設備と計画が重視される。 |
| 欠格要件 | 罰金刑、暴力団排除など | 欠格要件に廃掃法や関連法令の違反が加わる | 法律違反に対する行政処分の基準がより厳しい。 |
必須の知識要件:「講習会」の受講
産廃処理業の許可申請では、経営者が「日本産業廃棄物処理振興センター」などが実施する講習会を受講し、修了証を取得することが必須です。これは建設業許可にはない、産廃処理業特有の重要な要件です。
5|建設業者が取るべき適法な廃棄物処理の3つの戦略

「自社の事業で出た産廃だから」という誤解を捨て、適法な体制を構築するため、建設業者が取るべき具体的な戦略は以下の3つです。
戦略①:許可を取得せず「自家運搬」に徹する
自社の排出物を、自社の車両・人員で運搬し、運搬先(最終処分場など)への引き渡しのみを行うシンプルな体制です。
- メリット: 産廃処理業の許可申請・維持の手間と費用が一切不要。
- デメリット: 下請け業者や他現場の廃棄物を一切運べないため、柔軟な現場対応ができない。現場で廃棄物を一時的に「積替え・保管」する場合、別途積替え保管の許可が必要になるリスクがある。
戦略②:専門業者への「外部委託」を徹底する
自社で一切の運搬を行わず、すべての廃棄物を許可を持つ産業廃棄物収集運搬業者に委託します。
- メリット: 自社で許可を取得する必要がなく、運搬時の法令遵守リスクを回避できる。
- デメリット: 運搬コストがかさむ。委託先の業者が無許可であったり、不適正処理を行った場合、排出事業者である自社にも責任が及ぶ(連帯責任)ため、業者選定に細心の注意が必要。
戦略③:「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する
自社排出物だけでなく、下請けの排出物や他社の廃棄物も適法に運搬できるように、収集運搬業許可を取得します。
- メリット: 柔軟な現場対応が可能になり、廃棄物処理に関する収益化(コストセンターからプロフィットセンターへ)の道も開ける。
- デメリット: 許可申請費用と手間がかかる。5年ごとの更新や、毎年提出が義務付けられている「事業報告書」の作成など、継続的な法令遵守体制の維持が必要。
6|結論:建設業許可は「工事の請負資格」、産廃許可は「運搬・処分の資格」

建設業許可と産業廃棄物処理業の許可は、それぞれ「工事を請け負う資格」と「廃棄物を運搬・処分する資格」という、全く異なる視点から事業を規制するものです。
建設業許可を取得していても、自社の事業で排出されたものであっても、運搬行為が「他人の廃棄物を運ぶ」とみなされるケース(特に下請けの排出物を運ぶ場合)は多々あります。
自社の事業形態や現場体制を今一度確認し、少しでも「他人の廃棄物を運んでいる」可能性があれば、産業廃棄物収集運搬業許可の取得、または信頼できる専門業者への委託徹底を選択することが、無許可営業という重大なリスクから会社を守る唯一の道です。
ご自身の事業がどちらに該当するか判断に迷う場合は、建設業許可と廃棄物処理法の両方に詳しい専門家(行政書士)に相談することをおすすめします。
弊所のご紹介
弊所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。
建設業許可はもちろん、産業廃棄物収集運搬業許可も取扱っております。ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元、型枠大工の行政書士が全力でお客様の事業をサポートいたします。

また、弊所の取り組みとして近年現場で導入が進んでいる「建設キャリアアップシステム」や「グリーンサイト」、「buildee」の登録代行も、建設業許可と合わせて行っております。
もちろん、「登録代行だけ」「建設業許可だけ」も大歓迎です。気になった方は是非、下記サイトをご覧ください。