建設業の「決算変更届」とは?自分でできる?代行費用を節約する作成手順
建設業の「決算変更届」とは?自分でできる?代行費用を節約する作成手順

建設業許可において、毎年義務付けられている「決算変更届(事業年度終了届)」の提出は、建設業許可を適切に維持していく上での重要業務です。この手続きは書類が多く専門的であるため、「毎回専門家に頼んでいる」と行政書士に全て丸投げしている方も多いのではないでしょうか。
しかし、ポイントさえ押さえれば、代行費用をかけずに正確に提出することは十分に可能です。この完全ガイドでは、決算変更届の義務とリスクから、代行費用を節約するために自分で作成するための具体的な手順と重要チェックリストまでを、網羅的に解説します。
目次
1|「決算変更届」とは何か?義務とリスクを理解する
1. 提出は「年次報告」として建設業者の義務
決算変更届とは、建設業許可を取得した事業者が、毎事業年度の終了後、その1年間に行った工事の実績や財務状況を、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に報告するために提出する法定書類です。
これは建設業法第11条で義務付けられた年次報告であり、許可の信頼性と維持に直結する重要な手続きです。
| 項目 | 概要 |
| 提出義務者 | すべての建設業許可業者(一般・特定問わず) |
| 提出期限 | 事業年度終了の日から4か月以内 |
| 提出先 | 許可を受けた行政庁(都道府県庁の建設業担当課など) |
2. 提出を怠ると代償は「数万円」では済まない
提出義務を怠ると、代行費用を節約した以上に大きな不利益を被ります。
- 許可の失効リスク(最悪の事態): 5年ごとの許可更新手続きの際、過去の決算変更届に未提出分がが1回分でもあると申請は受理されません。期限内に更新できなければ、許可は失効し、500万円以上の工事を請け負えなくなります。
- 公共工事の受注機会の喪失: 国や自治体の入札に必要な経営事項審査(経審)は、この届出の提出が大前提です。未提出では経審に進めず、事業拡大の機会を失います。
- 企業の信用低下: 建設業許可は一般に閲覧公開されるため、不備や未提出はコンプライアンス意識の欠如と見なされ、金融機関の融資や新規取引に悪影響が出ます。
2|自分で作成して代行費用を節約する手順(5ステップ)

結論、決算変更届は自分で作成・提出することが可能です。行政書士への代行費用を節約できるほか、自社の財務状況や工事実績を深く把握し、経審対策への応用ができるメリットもあります。
以下の5つのステップで、迅速かつ正確に手続きを進めましょう。
Step 1:根拠資料の入手と最新様式の確保
まずは税理士と連携し、確定申告書と税務署提出用の決算書一式を受け取ります。これがすべての数字の根拠となります。次に、許可を受けた都道府県庁のウェブサイトから最新年度の決算変更届の様式をダウンロードします。古い様式は受理されないため、必ず最新版か、行政庁が指定する年度の様式であることを確認してください。
Step 2:必須の書類と資料を収集する
決算変更届に必要な主要書類は多岐にわたりますが、主に以下の書類を準備します。
- 変更届出書(都道府県によって呼び方が違う場合があります)
- 工事経歴書(様式第2号):1年間の完成工事を記載。
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号):過去3年間の工事高の推移。
- 財務諸表一式:建設業法に沿った形で作成します。(最重要)
- 納税証明書:法人事業税(知事許可)または法人税(大臣許可)の納税証明書が必要です。
変更があった場合には下記の書類も必要です。
- 使用人数(様式第4号)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
- 定款
- 健康保険等の加入状況
Step 3:最大の難関!財務諸表の「建設業法様式」への読み替え
ここが、専門家への依頼費用が発生する最大の要因であり、自分で作成する際の最大の壁です。税務申告用の決算書を、建設業法が定める特定の勘定科目と様式に置き換えなければなりません。
- 完成工事原価報告書: 税務上の売上原価を「材料費」「労務費」「外注費」「経費」などに細かく分類し直す作業が必須です。この分類は、経審の評価項目にも影響します。
- 注記表・株主資本等変動計算書: 法人の場合はこれらも必須書類であり、特に注記表は、会計方針や継続企業の前提など、建設業法特有の記載が求められます。
- 勘定科目の振り分け: 税務会計の「未成工事支出金」や「工事未払金」などが、建設業法様式の貸借対照表上の適切な位置に振り替えられているか確認します。
Step 4:工事経歴書(様式第2号)の正確な記載ルール厳守
工事経歴書には、その年度に完成した主要な工事を記載します。ルールは行政庁によって細かく定められており、ミスが多い箇所です。
- 記載件数: 多くの行政庁では、「請負金額の大きい順に10件」や「完成工事高の70%に達するまで」といった記載ルールがあります。必ず許可行政庁の最新の手引きを確認してください。
- 業種分類の厳守: 複数の業種で許可を受けている場合、業種ごとに工事経歴書を作成しなければなりません。
Step 5:納税証明書の取得と期限内提出
法人の場合は法人事業税、個人事業主の場合は個人事業税の納税証明書を取得します。未納や滞納がないことが証明されなければ、受理されません。
書類がすべて揃ったら、正本と副本(控え)の2部を準備し、事業年度終了後4か月以内という期限を厳守して窓口に持参するか郵送で提出して完了です。副本には必ず行政庁の受付印を押してもらい、厳重に保管してください。
3|【代行費用を節約!】自分で作る人の最重要チェックリスト

以下の項目は、行政庁から差し戻しを受ける原因として特に多い、重要事項です。提出前に必ず確認してください。
1. 税込・税抜きの統一と経審対策
経審を受ける予定がある場合、財務諸表と工事経歴書のすべての数字が消費税抜きの金額で統一されていることが必須です。税込で作成すると、経審の際に書類全体を税抜きに直す手間が発生するか、最悪の場合、経審の申請自体が遅延・差し戻しとなります。
2. 数字の「整合性」は1円たりとも許されない
行政庁が最も厳しくチェックする点です。以下の項目は、1円単位で完全に一致している必要があります。
- 完成工事高の整合性: 損益計算書の完成工事高合計 = 工事経歴書の請負代金の合計
- 貸借対照表のバランス: 資産合計 = 負債・純資産合計
- 利益額の一致: 損益計算書の当期純利益 = 株主資本等変動計算書の当期純利益
3. 提出書類の漏れと特例の確認
- 添付資料の確認: 提出する年度で役員変更や専任技術者の変更などがあった場合、決算変更届とは別に「変更届」の提出も必要となります。これらの書類が漏れていないか確認しましょう。
- 個人事業主の様式: 個人の場合、法人とは異なる様式を使用する点を再確認します。
- 附属明細表: 資本金1億円超、または負債合計200億円以上の会社のみ必要となる書類であり、該当する場合は作成漏れがないか確認します。
4|まとめ:代行費用を節約し、許可を確実に守る
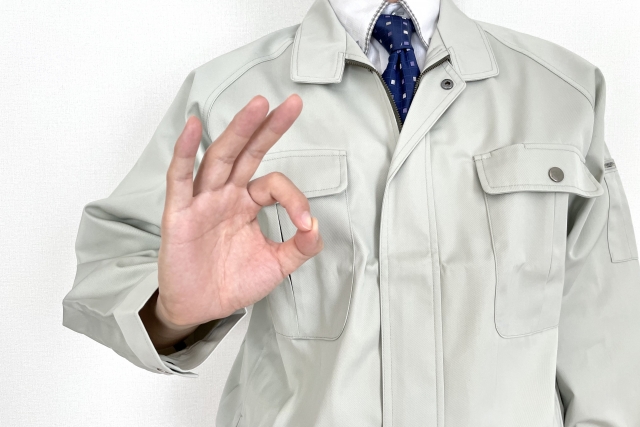
建設業許可の「決算変更届」は、その専門性の高さから行政書士に依頼されがちですが、代行費用を節約し、自社の力で解決することは可能です。
この手続きは、単なる事務作業ではなく、建設業許可の維持であったり、公共工事への足がかりとなる経審の基を築く重要な手続きです。自分で作成することで、費用を節約できるだけでなく、書類一つ一つの意味を理解し建設業許可業者としての体制が強化されます。
今回解説した手順とチェックリストを参考に、事業年度終了後4か月以内という期限を厳守し、確実に提出を完了させましょう。




“建設業の「決算変更届」とは?自分でできる?代行費用を節約する作成手順” に対して1件のコメントがあります。