【群馬県】建設業許可の取得にあたってしておきたい事前準備を行政書士が徹底解説!
【群馬県】建設業許可の取得にあたってしておきたい事前準備を行政書士が徹底解説!

建設業許可は、建設事業者様の事業拡大において不可欠です。しかし、申請手続きはその複雑さから、多くの事業主様にとって大きな負担となりがちです。
特に新規の申請では、必要書類の多さ、要件の厳密な解釈、そして行政庁による実態確認の徹底により、「書類を提出すれば終わり」とはなりません。
また、都道府県によってローカルルールが若干異なり、「〇〇県では証明書類はこれで認められたのに」なんてことも多々あります。
「申請書類を提出したものの、不備指摘で何度も役所へ足を運んだ」 「要件を満たしていると思い込んでいたが、過去の資料が揃わずゼロからやり直しになった」
この記事では「群馬県知事許可」に焦点を当てて、群馬県での建設業許可申請に特化した行政書士が、「申請前」に必ずチェックし、準備しておくべき6つの主要要件と、群馬県特有のローカルルールを徹底的に解説します。これから群馬県で建設業許可の取得をお考えの方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
1|群馬県知事許可の基本:「許可が必要な工事」の境界線

まず、事業が本当に建設業許可を必要とするのかを確認しましょう。許可が不要な「軽微な建設工事」は以下の通りです。
- 建築一式工事:請負金額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
- その他の専門工事(28業種):請負金額が500万円未満(消費税込み)の工事
これらの金額を超える工事を群馬県内の営業所を通じて請け負う場合、「群馬県知事許可」が必要です。
因みに、営業所が群馬県内のみの場合は「群馬県知事許可」。他の県にも営業所が存在する場合(例:群馬県に本店があり、埼玉県にも「熊谷支店」がある場合)は「国土交通大臣の許可(大臣許可)」が必要となります。
別記事:建設業許可の大臣許可・知事許可の違いとは?行政書士が分かりやすく解説!
群馬県申請におけるローカルルールと注意点
先述した通り、建設業許可は地域によって独自のローカルルールが様々です。
群馬県では以下の要件が厳しくチェックされます。
- 営業所の独立性の厳格化:
- 独立性の徹底:申請時、営業所について詳細な写真提出が求められます。自宅兼事務所の場合、居住スペースや他事業者の空間と物理的・機能的に完全に区分されていることが求められます。単にカーテンなどで仕切られていたりするだけでは認められない場合が多いです。入口は別で、壁等でしっかりと仕切られている形が理想です。
別記事:【建設業許可の要件】営業所として認められる要件とは。自宅でもOK?行政書士が徹底解説!
- 独立性の徹底:申請時、営業所について詳細な写真提出が求められます。自宅兼事務所の場合、居住スペースや他事業者の空間と物理的・機能的に完全に区分されていることが求められます。単にカーテンなどで仕切られていたりするだけでは認められない場合が多いです。入口は別で、壁等でしっかりと仕切られている形が理想です。
- 実務経験証明の厳密な審査:
- 後述の専任技術者要件において、実務経験証明書に記載された工事が、申請業種と密接に関連しているかを厳しく審査されます。単なる「付随工事」や「雑工事」と判断されると、経験年数として認められません。取りたい業種の実務経験として証明できるかどうかの判断が難しい場合は、事前に担当窓口に相談しましょう。
もし、申請種類を作成している途中で「実務経験として認められない」と判明した場合、それまでかけた労力が無駄になってしまします。事前の相談は非常に重要です。
- 後述の専任技術者要件において、実務経験証明書に記載された工事が、申請業種と密接に関連しているかを厳しく審査されます。単なる「付随工事」や「雑工事」と判断されると、経験年数として認められません。取りたい業種の実務経験として証明できるかどうかの判断が難しい場合は、事前に担当窓口に相談しましょう。
その他の都道府県では「証明するため書類が多く必要」であったり、「写しではなく原本が必要」など様々な独自のルールがあるようです。
2|許可の成否を分ける!「6つの主要要件」の事前準備

申請を円滑に進めるためには、6つの主要な要件を申請前に満たしているかを確認し、その裏付けとなる資料を準備することが最も重要です。
この6つの要件自体は全国共通です。都道府県独自のルールは、それぞれの証明方法にある場合が多いです。
要件1:経営業務の管理責任者(経管)の裏付け準備
「経管」は、会社の経営を適正に管理する能力を有する者であり、会社の信頼性の核となる要件です。
| 確認事項 | 必要な準備・証明資料 |
| 経験年数 | 個人事業主、役員として5年以上の経験があるか。 |
| 常勤性 | 申請する営業所に常勤しているか。健康保険証の写し(被保険者証)や役員登記簿謄本で確認。 |
| 経験の裏付け資料 | 5年分の確定申告書、当時の請負契約書・注文書など、「建設業の経営に携わっていたこと」を証明する資料を事前にファイリング。 |
要件2:営業所ごとの営業所技術者(旧専任技術者)の厳密な準備
営業所技術者(旧専任技術者)は、該当する建設工事に関する専門知識を持つ技術者です。許可取得を目指す上で、最も「不備」が出やすい項目です。
1. 資格ルートの場合
- 資格の有効性の確認:取得したい業種に対応した国家資格(例:土木一級施工管理技士、電気工事士など)の免状や合格証書の写しを準備します。
最も不備が出やすいと前述しましたが、該当資格を保有している場合はスムーズに進めることが出来ます。
資格+〇年の実務経験が必要といった資格もあります。(技能検定2級等)
2. 実務経験ルートの場合:「取りたい業種」と「経験業種」の合致
実務経験で申請する場合、単に「建設工事を10年やった」だけでは不十分です。
- 経験年数:指定学科卒業後の実務経験(大卒3年、高卒5年)または10年以上の実務経験があるか。
- 実務経験証明書の作成:
- この経験は、申請する「業種」に限定されます。例えば、内装仕上工事業の許可が欲しい場合、10年間の実務は「内装仕上工事」でなければなりません。
- 過去10年間の請負契約書、注文書、請求書などを集め、実務経験証明書に記載する工事名、期間、請負金額と相違がないか、一つ一つ照合する作業が必須です。
- 群馬県では、特に「どの工事がどの業種に該当するか」の判断が難しいため、事前に行政書士による資料精査が極めて重要です。
要件3:財産的基礎または金銭的信用(500万円)の準備
事業を安定して継続するための資金力を証明します。
| 確認事項 | 必要な準備・証明資料 |
| 自己資本の確認 | 直前の決算書で純資産合計額が500万円以上あるか。 |
| 残高証明書 | 自己資本が500万円未満の場合、金融機関から500万円以上の残高証明書を発行してもらいます。 |
| 取得のタイミング | 残高証明書は申請直前(発行から原則1ヶ月以内)のものが求められるため、申請書類がほぼ完成or完成の目途が立ったタイミングで取得できるよう調整します。 |
要件4:誠実性・要件5:欠格要件の徹底チェック
建設業を営んでいくにあたり誠実性があるか、申請者、役員、法定代理人などが過去に法令違反をしていないかを確認します。
誠実性に関しては、書類等は特に無いです。欠格要件は該当していないことの誓約書の提出が必要になります。
別記事:【知らなかったでは済まされない】建設業許可の欠格要件とは?代表者・役員が注意すべきポイント
- 公的証明書の取得:役員等全員について、本籍地の市町村役場で発行される「身分証明書」と、法務局で発行される「登記されていないことの証明書」を取得します。
- 重要:これらの公的書類には3ヶ月の有効期限があるため、申請書類の作成が進み、提出が確実になってから取得するよう計画します。
要件6:適切な社会保険への加入
法令に基づき、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が義務付けられています。
別記事:【建設業許可の要件】適切な社会保険とは?ケース別に徹底解説!
- 加入証明書の準備:未加入の場合は、許可申請前に速やかに加入手続きを完了させ、年金事務所やハローワークから発行される加入証明書類を準備します。
3|【群馬県】最短取得のための事前準備チェックリスト

事前準備として、どういったことをしていけばよいのかを簡潔にとまとめました。ご自身での申請の場合はもちろん、行政書士に依頼するといった場合でも、事前準備をしておくとよりスムーズに許可を取得することができます。
| 準備フェーズ | チェック項目 | 群馬県申請の重要度 | 備考 |
| 要件確認 | 経管、専技の資格・経験年数が明確か? | 高 | 特に専技は「取りたい業種」との整合性を確認。 |
| 営業所 | 営業所が自宅や他社と完全に区分されているか? | 高 | 自宅兼営業所で不備になりやすいポイント。 |
| 資料収集 | 経管・専技の裏付けとなる過去の契約書・請求書が5年分/10年分揃っているか? | 高 | 全て集めてから申請へ進む。 |
| 費用準備 | 法定費用(9万円)と行政書士報酬の資金(依頼する場合)を確保済みか? | 中 | 残高証明取得に影響がないか確認。 |
| 公的書類 | 役員等の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の取得時期は適切か? | 高 | 有効期限(3ヶ月)切れによる再取得を防ぐ。 |
| 社会保険 | 法定の社会保険に加入済みで証明書が手元にあるか? | 高 | 未加入の場合は要件を満たせず不許可となる。 |
4|まとめ:事前準備をしっかりとして、群馬県での許可取得へ

建設業許可の取得は、群馬県で事業を拡大したい建設業者様にとって避けて通れない道です。そして、その成否は「申請前の徹底した事前準備」にかかっていることをご理解いただけたかと思います。
特に、群馬県の厳格な営業所の実態審査や、専任技術者の「実務経験と申請業種の関連性」の証明といった細かい部分を事前にクリアしておくことが、許可取得の遅延を防ぎ、事業機会を逃さない唯一の方法です。
「本当にこの書類で大丈夫だろうか?」「うちの会社は要件を満たしているのだろうか?」
このように少しでも不安を感じた時は、専門家である行政書士へご相談ください。
群馬県の建設業許可申請に特化した弊所は、元職人(型枠大工)の行政書士が複雑な要件確認や膨大な書類作成を代行し、最短・確実なルートで許可を取得できるよう全面的にサポートいたします。
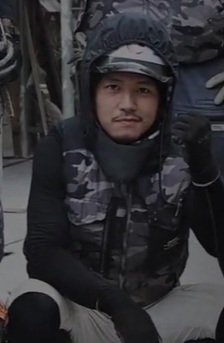
許可取得後の決算変更届や更新手続きといった、許可を維持するための継続的なサポートもお任せください。
許可取得という大きな一歩を踏み出し、群馬県での事業をさらに発展させていきましょう。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。



