解体工事業登録は「資格不要」で取得可能?技術管理者になるための実務経験ルートを解説
解体工事業登録は「資格不要」で取得可能?技術管理者になるための実務経験ルートを解説

これから解体工事業を始めたいと考えている事業者の方にとって、「解体工事業登録」は避けて通れない最初のステップです。
特に、その要件の一つである「技術管理者」について、「特定の国家資格がないと登録できないのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。
ご安心ください。結論から言うと、解体工事業登録の技術管理者は、特定の国家資格がなくても、「実務経験」だけで要件を満たし、登録することが可能です。
本記事では、この「資格不要」で登録を目指すための具体的な実務経験ルートと、行政書士だからこそ知っている実務経験の証明でつまずかないための重要ポイントを徹底的に解説します。
これから解体工事業登録をお考えの方に、少しでも参考にしていただけると幸いです。
目次
1|なぜ解体工事業登録が必要なのか?
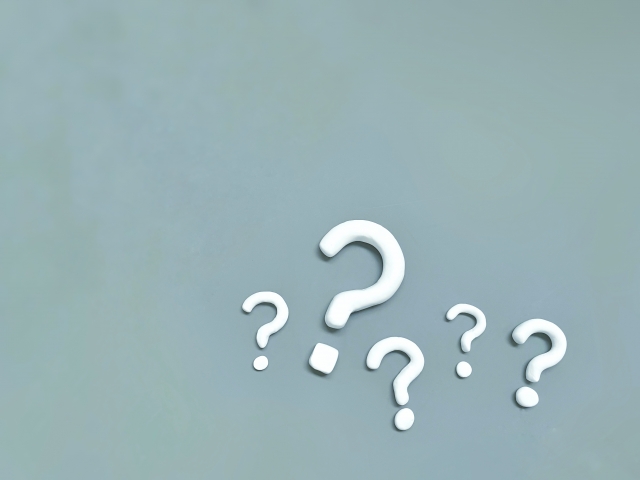
まず、解体工事業登録とは何か、そしてなぜ多くの事業者に必要となるのかを整理します。
1. 「500万円の壁」と解体工事業登録
建設業において、請負金額が税込500万円未満の工事を請け負う場合、原則として建設業の許可は必要ありません。これを「軽微な建設工事」と呼びます。
しかし、解体工事については、この「軽微な建設工事」に該当する500万円未満の解体工事のみを請け負う場合であっても、建設業許可(解体工事業)とは別に、都道府県知事への「解体工事業登録」が必要と法律で定められています。
別記事:解体工事業とは?どんな工事の内容が当てはまる?建設業許可取得に役立つ資格も併せて解説!
| 項目 | 解体工事業登録 | 建設業許可(解体工事業) |
| 請負金額の基準 | 500万円未満の解体工事のみを行う場合 | 500万円以上の解体工事を請け負う場合 |
| 法的根拠 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) | 建設業法 |
| 有効期間 | 5年間(更新が必要) | 5年間(更新が必要) |
ポイント: 建設業許可(解体工事業)を取得している場合は、解体工事業登録は不要です。しかし、まずは500万円未満の工事からスタートする場合、より要件が緩やかな「解体工事業登録」を目指すのが一般的です。
2. 登録がないとどうなるか?
解体工事業登録がない状態で500万円未満の解体工事を請け負うと、建設リサイクル法違反となり、罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象になる可能性があります。必ず登録をしてから営業を開始しましょう。
2|技術管理者になるための「資格不要」ルート

解体工事業登録の要件の一つに、営業所ごとに「技術管理者」を常勤させることがあります。この技術管理者が、解体工事の適正な施工を確保する役割を担います。
建設業許可で例えると、「営業所技術者」にあたる人的要件のことです。
特定の国家資格がない場合でも技術管理者になるために利用できるのが、「実務経験」によるルートです。
1. 最も一般的な実務経験ルートは「8年以上」
特定の学歴や資格がない方が技術管理者になるための要件は以下の通りです。
| 区分 | 必要とされる実務経験年数 | 備考 |
| 特定の資格・学歴がない者 | 8年以上 | 解体工事に関する実務経験 |
つまり、直近に解体工事の経験が8年以上あれば、国家資格を持っていなくても技術管理者として認められるのです。
建設業許可の「営業所技術者」に実務経験のみでなる場合、10年の実務経験が必要なので、全体的に要件が緩やかになっていると言えます。
2. 学歴や講習による実務経験の短縮
もし、特定の学歴がある場合や、指定の講習を受講している場合は、必要な実務経験年数を短縮できます。2日間の講習となっています。受講料は3万円弱です。
| 学歴/講習 | 実務経験(通常) | 実務経験(講習受講者) |
| 大学・高専の指定学科卒業 | 2年以上 | 1年以上 |
| 高校の指定学科卒業 | 4年以上 | 3年以上 |
| 上記以外(一般的なルート) | 8年以上 | 7年以上 |
※指定学科:土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科
【注目】 最も一般的な「8年以上」のルートでも、(公社)全国解体工事業団体連合会などが実施する「解体工事施工技術講習」を受講し修了することで、必要な実務経験年数を7年に短縮することが可能です。1年分の期間短縮は、これから事業を始めたい方にとって大きなメリットとなります。
3|実務経験の「証明」こそ最大の難関
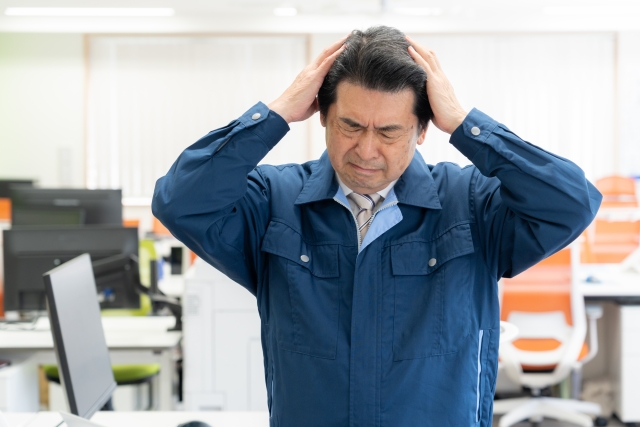
「8年または7年の実務経験がある」と口で言うのは簡単ですが、解体工事業登録において最も難易度が高いのが、その実務経験を客観的な書類で証明することです。
行政書士がサポートするケースの多くは、この「証明書類の収集・作成」でつまづいています。
1. 実務経験として認められる内容
技術管理者としての実務経験とは、「解体工事の施工を指揮、監督した経験」や「実際に解体工事の施工に携わった経験」を指します。
【重要】実務経験として認められないケース
- 単なる雑務・事務・営業の経験:技術的な経験ではないため認められません。
- 無許可業者での経験:実務経験として認められるのは、解体工事業登録、または建設業許可(とび・土工工事業、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を取得している業者での経験に限られます。
- 実務経験が重複している期間:複数の会社で同時期に勤務していたとしても、重複した期間は二重にカウントすることはできません。
2. 実務経験の証明に必要な書類
実務経験ルートで申請する場合、主に以下の書類が必要になります。
① 実務経験証明書(申請書式)
過去に所属していた会社(事業主)に、いつからいつまで、どのような工事に携わっていたかを証明してもらう書類です。
② 経験を裏付ける客観的証拠
これが最も重要です。実務経験証明書の内容が真実であることを裏付ける、客観的な証拠を提出しなければなりません。
- 工事請負契約書・注文書の写し:申請者氏名が載っていなくても、所属した会社の工事実績を裏付けるものです。
- 施工状況の写真・図面:申請者が現場で技術的な役割を果たしていたことが分かる資料。
- 会社が許可・登録を受けていた証拠:過去の会社の解体工事業登録証、建設業許可証の写しなど。
- 常勤性の証明:健康保険証の写し(事業所名を確認)、賃金台帳、源泉徴収票など。
③ 過去の所属会社が既に廃業・倒産している場合
証明書(様式)に署名・捺印をしてもらうことができない場合は、自己証明や、過去の確定申告書、給与明細、年金記録などで客観性を補完する必要があります。この手続きは複雑で、行政書士の専門知識が必須となります。
4|解体工事業登録の全体像と行政書士の役割

解体工事業登録は、技術管理者要件以外にも、「欠格要件」や「登録手数料」など、確認すべき事項があります。
1. その他の要件(欠格要件のチェック)
申請者(法人または個人事業主)やその役員等が、以下の欠格要件に該当していないことが求められます。
- 登録を取り消されてから2年を経過していない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法などに違反し、罰金以上の刑に処せられてから2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に該当する者
2. 登録の申請先と費用
- 申請先: 解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事に登録申請を行います。複数の都道府県で工事を行う場合は、工事を行うすべての都道府県に登録が必要です。
- 登録手数料: 各都道府県により異なりますが、33,000円~45,000円程度が必要です。
3. 行政書士に依頼するメリット
特に「資格不要」の実務経験ルートで登録を目指す場合、行政書士は以下のようなサポートを提供します。
- 実務経験の「適合判断」: お客様の職歴や過去の工事実績をヒアリングし、自治体の基準に照らして実務経験が要件を満たしているかを事前に判断します。
- 証明書類の準備代行: 過去の会社が廃業している、証明書の記載内容に不安があるなど、複雑なケースでの客観的な裏付け資料の収集・作成をサポートします。
- 効率的な申請: 複数の都道府県への同時申請や、建設業許可へのステップアップを見据えた申請書類の準備など、事業展開に応じた最適な手続きを支援します。
5|まとめ:まずは8年間の実務経験を整理しよう
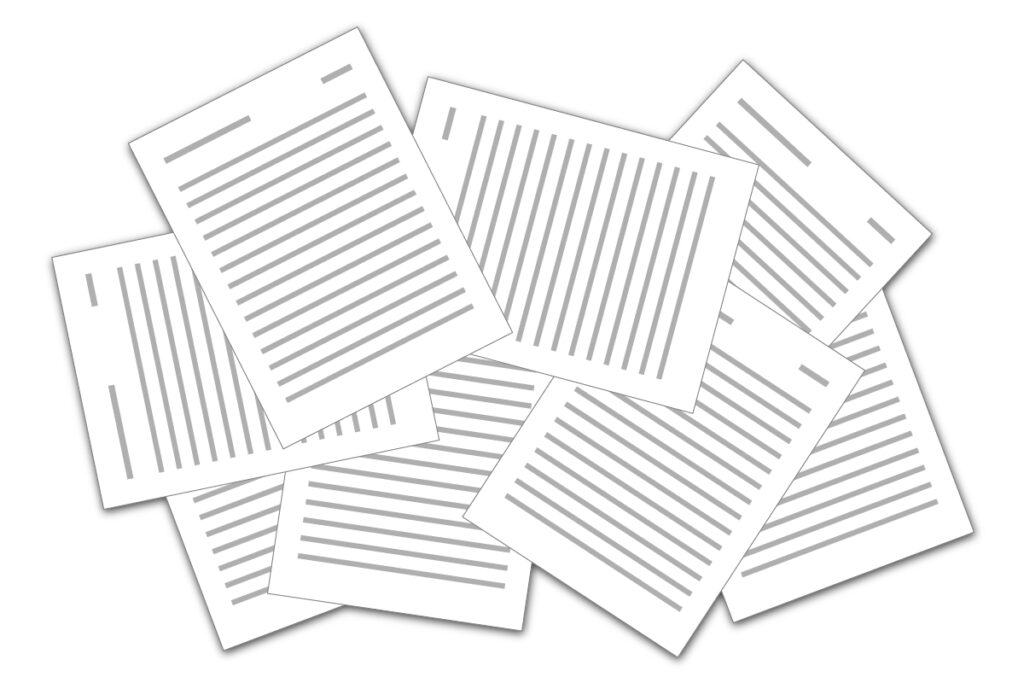
解体工事業登録は「技術管理者」さえ確保できれば、国家資格がなくても取得可能です。そのための王道ルートが「8年(または7年)の実務経験」による申請です。
しかし、その道のりで最大の壁となるのが、曖牲な実務経験ではなく、公的な書類で「解体工事の実務」を証明する作業です。
これから解体工事業を始めたい方は、まずは自身の職務経歴、特に過去8年間の解体工事への関わり方を正確に整理することから始めましょう。
もし、実務経験の証明に不安がある、過去の勤務先との連絡が難しいといった場合は、速やかに行政書士にご相談ください。専門家が、あなたの確かな経験を「適法な書類」として行政庁に伝えることができます。
解体工事業登録をスムーズに完了させ、さらなる事業拡大を目指していきましょう。



